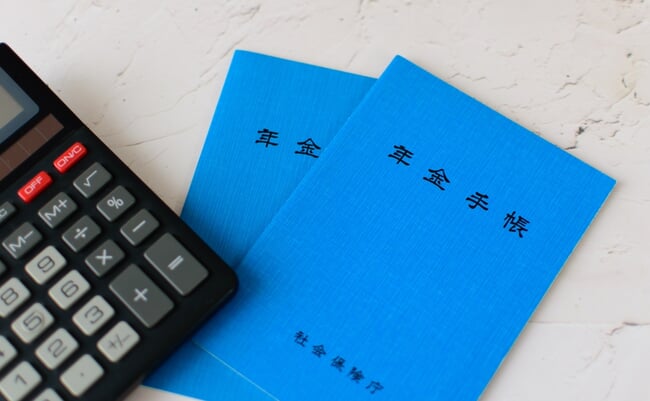年金以外の所得が多い高齢者に対し、老齢基礎年金(国民年金)を停止するか、支給額を減らすべきだというニュースが話題となっています。これは、年金財政の厳しさが再び注目される中での議論ですが、こうした問題は今に始まったものではありません。昭和から平成にかけて、日本の年金制度は大きな変遷を遂げてきました。高度経済成長期における年金の増額や高齢者医療の無料化は、当時の日本社会の繁栄を象徴するものでしたが、平成の時代に入り、経済の停滞とともに年金財政の厳しさが顕在化しました。本記事では、年金制度の拡大とその後の改革を振り返りつつ、政治と経済が年金政策に与えた影響を探ります。メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』では、こうした年金の歴史や仕組みを楽しく分かりやすくお伝えしています。ぜひ、ご登録の上、年金についてもっと学んでみてください。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:これからますます重要な役割となる年金制度の歩んだ道と今後の年金の課題の総括(2018年12月26日第65号改訂)
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ
支給する年金は増額するけど、保険料は値上げしないという黒歴史
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
1.昭和40年代までは年金も上がり続け、高齢者医療を無料にしたりもした。
平成という時代を振り返ってみると様々な甚大な災害もでしたが、経済の先の見えない停滞の時代でもありました。
そんな中で年金は苦しい立場に陥り、様々な改正に追われる事になります。
昭和の時代は高度経済成長の波に乗り、年金額も改正のたびに計算しなおされて増額の方向に向かっていきました。
昭和30年代から昭和40年代は特に景気が良く、賃金も年平均10%も上がっていくという今では考えられないような発展もありました。
現役世代の賃金が猛スピードで上がってしまうため、設定された年金額との差が大きくなってしまうので、年金も賃金の伸びを追いかけるかのように増額されていきました。
生活保障としての年金の役割を果たさせるためには、現役の賃金との差をあまりにも開かせるわけにはいかなかったからです。
賃金に対しての実質価値を保障する事が非常に大事な事でした。
年金の増額が激しい時代でしたが、そうなるともちろんその財源となる保険料は高くなってしまう。
ところが経営者団体としては負担が大きくなってしまうため、そしてその時々の政府も保険料の急激な引き上げには選挙に響くから反対し、当時の厚生省が保険料はこのくらい上げてほしいという事を訴えても、その案よりも低い保険料率で抑えられてきました。
つまり、年金の増額はいいけど保険料の増額はしないでねっていう都合のいい話が何度も行われてきてしまいました。
1955年から自民党と社会党の二大政党の時代となり、これを55年体制といいますが1993年の連立内閣として始まった細川護熙内閣が誕生するまではずっと自民党が与党として君臨しました。
ずっと自民党が政権を取っていたわけですが、所かしこに自分たちの政権を維持する事を優先するような事をやってきました。
保険料の引き上げ反対もそう。選挙に影響するのは控えないといけないから都合の悪い事は先延ばしにしてきてしまっていました。
歴史的に見ると、とにかく自民党は選挙で勝つ事、そして与党である事に最も価値を置きます。長年敵対した社会党と組んだり公明党と組んだり、与党であるためなら手段を選びません。
さて、いろいろ景気が良かったから攻めの社会保障で良かったんですが、その中でも究極なのは昭和48年にできた老齢福祉法だったと思います。
この老齢福祉法は70歳以上の老齢の人は医療費無料というものでした。昭和48年は田中角栄内閣の年ですが福祉元年ともいわれます。
東京都や秋田県が老人医療費の無料化をその前から老人医療費無料化をやり始めた事で、政府としても無料化をやらざるを得なくなってしまいました。
昭和45年に高齢化率7%以上になって高齢化が始まったにもかかわらず、無料で70歳以上の人は医療が受けられるようになりました。この老人医療費の無料化により乱診乱療という状態になり、病院がサロン化していきました。
老人医療費の無料化の先駆けは昭和30年代の岩手県の沢内村でしたが、無料化だけでなく老人の保健(健康を保つって事)活動にも力を入れていた。でも、全国的には無料化はただの人気取りだけに走ってしまうという事になった。
無料と保健活動(病気を予防するための活動)は本来は両輪なのであります。
人気取りの無料政策ががだんだん市町村の重荷となり、財政は悲鳴を上げ始めました。
ちょうど10年後の昭和58年に、老齢福祉法ではなく老人保健法に名を変え、定額の一部負担を高齢者に負担してもらうようになりました。
この時に高齢者の医療は、各制度(国保とか健保)の頭数に応じてお金を出し合うという拠出金(拠出っていうのは飲み代をみんなで出し合うとかいう意味)の仕組みが取り入れられました。
昭和61年にもその老人保健法の一部負担を増額していきましたが、何度か改正の内に平成20年に後期高齢者医療制度として75歳以上の高齢者には1割の負担をしてもらうようになりました。
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ
2.それぞれが独立していた昭和時代の年金制度と年金の抑制への変更。
ところで年金は昭和の時代は国民年金、厚生年金、共済年金というのは全て他の制度として独立しており、経済の著しい伸びに追いつくためにそれぞれが競い合うように増額していった。
例えば、昭和17年にできた厚生年金は昭和30年代は概ね月額3,500円程の金額でした。
本当は昭和29年の厚生年金大改正の時に保険料を引き上げたかったのですが、経済界からの強い抵抗で引き上げる事ができずにミニマムな給付に止まってしまいました。
これを機に、各職業団体が共済組合を設立して、自分たちは有利な年金を作ろうぜ!という動きが加速していきました。
そして中小企業団体(厚年加入者900万人のうち700万人くらい)にも、共済組合を作る動きが出てきたので魅力ある年金にする必要が出てきました。
その後に、昭和40年にこの金額を1万円になるように改正し、保険料率もそれまでの3.5%から5.5%までに大幅に引き上げました(経済界からの反発が強くなり、昭和41年の厚生年金基金の設立に繋がる)。
昭和44年には2万円に引き上げ、昭和48年にはその金額を5万円まで引き上げてさらに、現役世代の60%以上の給付を目指すという年金の実質価値を維持するというものに変わりました。
この昭和48年によく言ってきたように、物価の伸びに連動するように物価スライド制が導入されて、毎年年金額が変わるという動態的なものになりました。
毎年の物価の伸びで年金額が変わり、年金の積立では毎年変化する年金額には対応できないのでこの年あたりから、本格的に現役世代の保険料をその年の受給者に送るという賦課方式の方向に転換し始めました。
ただ、その時の現役世代がその時の受給者を支えるという賦課方式だと今後少子高齢化が進む中では将来の現役世代の負担を急激に強いてしまう恐れがある為、とりあえずはまだ段階的に保険料を引き上げながら対応するというやり方を続行していました。
高齢化は先ほども言ったように、昭和45年から本格的に始まりましたが、少子化は昭和50年から2.0を割り始めて少子化も本格化し始めました。
しかし、少子化に関しては昭和の時代というのはその話題はなんとなくタブー視されており、少子化対策基本法などの本格的な法律ができたのは平成15年になってからでした。
少子高齢化の進行とともに、昭和48年のオイルショックによる不況の始まりにより、各年金制度が競い合うように年金額を引き上げていった事が昭和50年代になると一転して、制度の存続が危ぶまれるようになりました。
年金額を上げすぎていってしまったため給付と保険料負担の是正、そして官民格差の是正や(共済年金はかなり有利な制度になっていたからその官民格差の解消)、制度の一元化を求める声が強くなりました。
年金額の増額から、給付の抑制と削減の方向に向かい始めたのが昭和50年代。
そして増税なき財政再建を目標に徹底した無駄の削減が進められ始めました。
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ
3.いずれ訪れるのが見込まれた産業の斜陽化が顕在化し始めた。
特にこの頃、国営だった国鉄(今のJR)は財政破綻の危機に陥っていました。
戦後に輸送力の増強と国策に従って大量に雇用した職員(戦後帰ってきた兵隊さんに仕事が無かったから国営だった国鉄に採用した)が昭和40年代になると一斉に退職し始め、また、昭和50年代の自動車の発展により国鉄の規模が小さくなっていきました。
昭和30年代は50万人くらいいた国鉄職員が、昭和50年代になると30万人ほどまで減少。
国鉄共済組合の年金受給者は大量採用した時の職員の退職が一気に急増し始め、昭和51年には保険料収入に対し年金の支出が上回り始め、赤字になりだしました。
保険料収入だけでは足りないから国鉄自身が積み立てていた積立金も取り崩しながら国鉄共済組合は年金を支払っていました。
なお、国鉄共済組合は非常に有利な年金を支給していました。
普通の民間の厚生年金は通常加入期間の全体の平均を取って年金額を算出しますが、国鉄は退職前の1年前の平均報酬での年金を支給していました。
共済年金は大体そういう有利な計算方法だったけれども、さらに国鉄は退職時に特別昇給した(ちょっとオマケで給与を上げてやったとかそういう)額で計算していたから、年金受給者にとっては嬉しいけど余計に国鉄の年金制度の負担を重くしていく事になります。
国鉄自身での年金支払いも限界になり始め、、、
(続きは下記よりご登録の上、お楽しみください。初月無料で続きを確認することができます)
続きの内容はこちら
4.昭和61年に年金の形が大きく変化した。
5.訪れた金融不況と年金。
6.年金給付を抑制する事で将来の年金受給者の年金水準が上がる。
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ
image by: Shutterstock.com