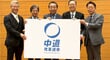かつての統治時代、台湾にさまざまな技術を伝えた日本。稲作においてもそれは例外ではありませんでした。今回のメルマガ『黄文雄の「日本人に教えたい本当の歴史、中国・韓国の真実」』では、今も台湾の人々が敬愛してやまない、彼の地の農業発展に尽力した日本人農学者の功績を紹介。その上で、彼らの精神にこそ日本が瀕している「令和の米騒動」解決のヒントがあると結んでいます。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:【台湾】コメ不足の今こそ日本人は「蓬莱米の父」磯永吉の精神に学べ
コメ不足の今こそ日本人は「蓬莱米の父」磯永吉の精神に学べ
● 蓬莱米育んだ小屋、日本時代の建設から100年 台湾大で記念式典
台北市の台湾大学構内にあり、日本統治時代の農学者、磯永吉が「蓬莱米」などの研究に取り組んだ木造建築「磯永吉小屋」(磯小屋)が、1925(大正14)年の建設から100年を迎えた。15日には記念式典が開かれ、AI(人工知能)で着色するなどした古写真などが公開された。
蓬莱米は日本種と台湾種の米を交雑させて生まれた新品種。磯小屋は台湾大の前身である台北高等農林学校の実習農場で最も早く建てられた建物の一つとされ、2009年に台北市の市定古跡に登録された。
日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表(大使に相当)はあいさつで、磯は蓬莱米を誕生させ、多くの酒類の原料を改良し、食糧と商品作物の価値向上に大きく寄与したと功績をたたえた。
● 蓬莱米育んだ小屋、日本時代の建設から100年 台湾大で記念式典
今、日本は米不足を解消するために政府が備蓄米を放出し、対応を急いでいます。米不足に陥ってしまった原因については、連日、メディアで専門家が様々な分析をしており、様々な要因が考えられるということですが、主に天候不良と減反政策を挙げる専門家が多いように思います。
自国民の食料を確保することは政府として最低限の責務であり、特に主食であるコメを確保しておくことは、政府にとって最重要事項です。それは、日本だけでなく米を主食とするアジア諸国においては同じことです。
台湾の米は、タイ米などの長細いものではなく、ジャポニカ米と同じ種類のもちもちとした食感が特徴の米で知られています。今では熱帯に属する位置にある台湾で、ジャポニカ米に属する米が生産できることは普通のことですが、そこに至るまでは長い道のりでした。
黄文雄は生前の著書で、台湾は日本時代を経て文明国となることができたということを、何度も言っています。戦前、台湾が当時の人口を維持するだけの食料を生産できたのは、日本時代、台湾の農業を発展させた日本人の尽力があったからこそだと。それ以前の台湾は飢饉の島だったとも言っています。
この記事の著者・黄文雄さんのメルマガ