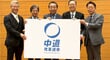では、その「BRA」には何と書いてあるのかというと、次のような内容になっています。
- 五輪が開催された場合にIOCは、放映権料を原資とするIOCから東京サイドへの拠出金を850億円払う
- 仮に放映権のキャンセルが発生した場合には、この拠出金を減額する
- この場合の減額は、放送局からのキャンセル額に「Tokyo2020パーセンテージ」を掛けた額である。この「Tokyo2020パーセンテージ」とは、「850億円/東京五輪における全ての放映権収入」という計算式となる
- 日本側の負担としては、当初拠出金として入るはずであった850億円が減額されるだけであり、それ以上の負担はない
このうち3.が少々複雑ですが、要するに全ての放映権収入について、IOCと東京の取り分が2:8だとすると、「Tokyoパーセンテージ」は80%になります。その上で、仮に1,000億円のキャンセルがあったとしたら、東京サイドはもらえるはずの850億円の中から800億円を返金するということになります。
ちなみに、入手した契約ドラフトによれば、この「BRA」契約のサイナー(署名者)は武藤敏郎氏、つまり2020東京オリ・パラ実行委の事務総長です。武藤氏は、この間、中止となった場合の違約金について「見当がつかない」とか「考えたことがない」などと発言していますが、仮に「開催都市契約+BRA」の枠組みがしっかり合意できているのであれば、そんなにウロウロする必要はないわけで、こうした発言を繰り返しているのは奇々怪々という感じがします。
それだけではありません。2020年9月29日に東京サイドとIOCが締結している「1年延期に伴う契約改定(アメンドメント4)」には、仮に開催ができて余剰金が発生した場合には、「例外的な状況(パンデミックによる延期)」にかんがみてIOCは20%の「取り分を放棄する」としています。
勿論、この点について言えば、こんな状況で強硬開催した場合には「余剰金」つまりイベントとしての「もうけ」が出る可能性は低いわけで、空虚な善意とでも言うべきものですが、それはともかく、基本的に全収入におけるIOCと東京サイドの取り分というのは「2対8」という感触であることはわかります。
そんなわけで、ここまで述べてきた「開催都市契約+BRA」という枠組みであれば、IOCのバッハ会長が「ぼったくり」というのは印象論であって、IOCと東京サイドの間は比較的明朗会計になっていると言って良いと思います。まして、違約金が発生という可能性は低いし、IOCにしてもダメージについては保険でカバーする措置を当然講じていると考えるのが妥当です。
では、どうして中止できないのか、また中止できない理由として、やはり金銭的事情があるのかというと、これはやはり日本国内の問題になると思われます。
まず考えられるのはスポンサー等の問題です。今回、スポンサー契約に関するBRAに相当する協定については、資料を入手できませんでした。ですが、ロンドンやリオに関する資料を見てみると、一般的に放映権料の半額近い金額がスポンサー料として入ってくる計算だと言われています。
このスポンサー契約に関しても、基本的にはIOCの契約のひな形が使用されて、万が一キャンセルが出た場合には、その枠内での返金ということになるはずです。
問題は、日本の多くの産業には、前近代的な「バーター取引」が残っている点です。つまり五輪のスポンサーになって拠出金を払うと、その見返りとしてメリットがあるというような取引です。勿論、開催都市契約にあるように、これが見える形になる場合はしっかりIOCのガイドラインで管理されるわけですが、何と言っても日本国内の場合は、見えない形で色々な利害とか口約束とかが残っている可能性はあります。