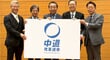ユーチューバーに相当する存在だった小池百合子や高市早苗
ただし、この新しい政党の出現自体は新しい現象というわけではない。例えば、昭和の時代からさまざまな諸派政党が存在していた。特に、1982年の公職選挙法改正で、参院選に比例代表制が導入されると、その数は激増した。
比例区に出馬するために、政党(制度上は「確認団体」という)の形をとらなければならなくなったからだ。これまで、全国区に個人として出馬していた候補などが「サラリーマン新党」「第二院クラブ」「福祉党」「MPD・平和と民主運動」「無党派市民連合」「雑民党」「教育党」「地球維新党」「UFO党」「日本世直し党」など「ミニ政党」を結成した。
「ミニ政党」の政治活動の中心はテレビだった。参院選の政見放送をかすかに覚えているが、「宇宙との交信」「交霊術」「呪文を唱える」「突然踊りだす」「ねずみ講の宣伝」など、やりたい放題だった。公職選挙法の範囲内で最大限の自由を与えたNHKには敬意を表したいところだ。
そして、参院には横山ノック、コロンビア・トップ、青島幸雄、野末陳平、野坂昭如、立川談志、扇千景、山口淑子(李香蘭)、山東昭子など、さまざまなテレビタレントが登場していた。
また、当時は田原総一朗の『朝まで生テレビ』、久米宏の『ニュースステーション』などの報道番組に政治家が登場し、政治的主張を直接国民に訴える「テレポリティクス」が始まりつつある時代だった。テレポリティクスの潮流は、「ミニ政党」だけではなく、既存の大政党にも広がった。90年代以降、「テレポリティクス」が生んだ政治家には、小池百合子、高市早苗、辻元清美、蓮舫、舛添要一、海江田万里らがいる。彼らは、現在のユーチューバーに相当する存在だったといえるのではないか。
「ガーシー現象」と類似する現象も起きた。1995年の東京都知事選だ。立候補した青島は、「カネのかからない選挙をする」と宣言して、選挙期間中一度も街頭演説に立たず、誰とも握手をしないなど選挙運動を一切せず、テレビタレント・放送作家として得た高い知名度・人気を生かして当選した。
要するに、現在の新しい政党の誕生という現象は、その舞台がテレビからユーチューブに移行しただけで、それ自体は新しい現象というわけではない。
一方、テレポリティクスとユーチューブでは大きな違いもある。それは、政治参加の規模が劇的に拡大したことだ。