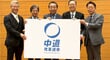「政治家を動かす」から「政治家になる」への変化
テレビは、「電波法」に基づいて、総務省から与えられた「放送免許」を持つテレビ局が、「放送法」の規定に従って番組を制作する。それに出演できる人は、特別なタレント性を持つ人に限られる。
一方、現代のSNSは、特別な人のためのものではない。誰でも使えて、世界に向かって意見を発信することができる。その意見に賛同した人たちが、リアルな人間関係を持たない、会ったことがない人同士が、ネットワークを形成できるようになった。
その結果、政治参加も劇的に拡大した。政治とはかかわりがなかった個人が、日常の思いを発信した結果、「#保育園落ちた日本死ね!」「#生理の貧困」などハッシュタグを使ったキーワードに多くの人が賛同し拡散した。その後、待機児童に関する議論が展開されて、安倍政権が政策を転換した。全国の自治体で生理用品配布の動きが進むようになった。個人のつぶやきが、政治を動かすようになったのだ。
そして、それは政治家を動かして実現しようとする動きから、自ら政治家になり、実現しようという動きに変化していった。地方議会は男性が8割以上にのぼり、60歳以上が市区町村議会の6割以上を占めてきた。
しかし、2023年4月の統一地方選では、子育て女性や若者が続々と立候補する動きが広がった。彼らは、従来の政治家と異なる方法で政治活動をした。仕事や子育てという日常生活を続けながら、街頭演説はほとんどせず、SNSで生活者の視点、若者や子育て世代に向けた政策を発信した。その結局、道府県議会、市議会、市長・区長で女性候補者・当選者数は過去最多となった。また、被選挙権を得たばかりの25歳の「最年少議員」が全国各地で誕生した。