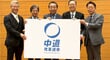関東甲信の梅雨入りは、過去最も遅い6月22日かさらに遅い23日になりそうとのこと。「梅雨入り」と言われれば、雨でも諦めがつく気がするから不思議ですが、実は「梅雨入り宣言」をしているのはメディアであって気象庁ではないようです。今回のメルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』では、気象予報士として『ニュースステーション』のお天気キャスターを務めていた健康社会学者の河合薫さんが、「梅雨」にまつわる気象庁の苦悩の歴史を紹介。今年の梅雨の傾向についても解説し、予想以上の豪雨に対する備えを呼びかけています。
梅雨の遅れと豪雨の関係
今年は梅雨入りが大幅に遅れていますが、昨日は西日本、東日本を中心に豪雨となりました。このタイミングで「梅雨入り宣言」してもよかったと思いますが、おそらく今日晴れる確率が高かったため、「次の雨まで待ちましょう」ってことになったのだと思います。
気象庁の職員にとって「梅雨入り宣言」は頭痛の種です。それは数年前から、気象庁が「梅雨入り」について表現方法も含めて二転三転させてきたことからもわかります。
そもそも気象庁は一度も「梅雨入り宣言」という言葉を使っていません。1964年から、「おしらせ」として梅雨入りの発表をメディア向けにしていたものを、マスコミが「梅雨入り宣言・梅雨明け宣言」という言葉で取り上げ、社会に広めたのです。
本来季節の変わり目は至極曖昧で、「はい!今日から夏です!」だの、「はい!今日から秋です!」だのと言い切れるものではありません。しかし一方で、美しい四季の中に存在する「梅雨」は、覚悟が必要な季節。気象庁が「おしらせ」を出していたのも、災害に備えてほしいとの思いがあったのでしょう。
私たちも、「はい!今日から梅雨です!」と気象庁が宣言してくれれば、雨が降っても「梅雨だから」と上手にあきらめ、晴れれば「ラッキー!」と前向きな気持ちになれます。メディアが生んだ「梅雨入り宣言」は、ちっとも科学的じゃない「人の感情」に上手く合致したのです。
ところが1990年代に入ったころからでしょうか、「梅雨明けしたのにまた雨ふってるぞ!」「梅雨入りしてないのか?ずっと雨続いているじゃないか!」といったクレームが気象庁に寄せられるようになりました。
あくまでも私の推察ですが、気象予報士の資格が社会の「お天気」への関心を高めたことも、クレームが増えたことに関係してるのかもしれません。
1994年に行われた1回目の試験で、私は運良く合格し気象予報士第一号となりましたが、その時頻繁に飛び交ったのが「ピンポイント予報」という言葉です。それまでの天気予報は気象庁の予報しか、不特定多数の人に公表できなかった。しかし、気象予報士の資格があれば「ピンポイントの予報をしてもいい」と気象業務法が改正されました。
そんな流れがあったことに加え、90年代は記録的な冷夏が発生したり、梅雨明けを明確に特定できない年が相次ぎ、さらには、記録的な猛暑が発生するなど、異常気象が頻発するようになりました。
この記事の著者・河合薫さんのメルマガ