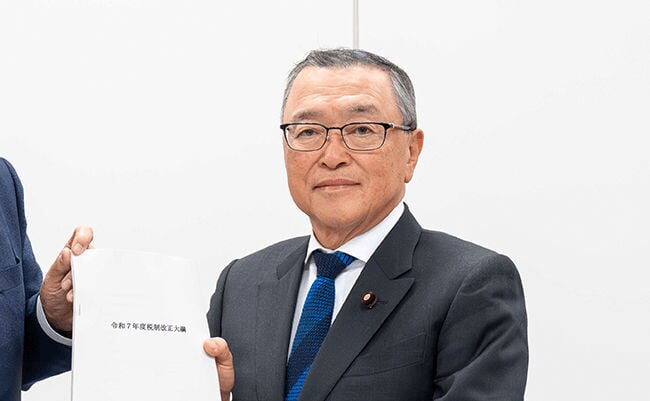セルフ経済制裁を続けた財務省のあやまち
財務省設置法第三条には同省の任務が以下のように定められている。
財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
健全な財政、適正かつ公平な課税。財務省はこれを金科玉条とする組織であり、国民の生活や幸福といったことは任務外なのである。減税して人々の懐を温め、消費をさかんにして国の経済を豊かにするという、仁徳天皇の「民のかまど」的な発想は必要とされない。任務を分ける各省の設置法が、省益の対立する縦割り構造を生み、予算編成を担い財源を配分する財務省の支配的な地位をつくりあげる。
もとより税は政治に左右されるべきではない。政治家は国民受けする減税政策に走りがちである。税調はそれを防ぎ、税制の安定性をはかるために存在する。
だが、30年以上にわたるデフレのもとで、税調が財務省の論理を優先し、減税よりも増税を強化してきたため、不況を抜け出せず、バブル崩壊後の1991年から経済成長率は低迷を続けてきた。
本来、不況期には減税して貨幣の流通量を増やし、好景気を冷やしたい時に増税するものである。ところが、財務省と自民党税調は財政健全化の名のもとに、国債発行を「悪」と決めつけて、緊縮財政策のための税制を採用してきた。
おかげで、いまや税と社会保障を合わせた国民負担率は45%をこえている。これでは人々の使えるおカネ、すなわち“手取り”が少なくなりすぎて、景気が上向くはずがない。
「インナー」と呼ばれる教条的な密室の政策決定が、この国の経済運営を硬直化させてきたのである。軽量級と評された宮澤税調の弱点をついて安倍政権は減税政策をめざしたが、予算編成を財務省の専門性に頼る以上、自ずから限界があった。
「税は理屈の世界」宮澤氏は財務官僚に毛が生えた“小ボス”
「税は理屈の世界です」。誰がそう決めたのか知らないが、 宮澤氏は政界における財務省的「理屈」の守護神であろうとしている。
「財政を健全に保つことは大変大事だと思いますし、現段階で日本国債が破綻することはないにしても、放漫財政を続けていると『キャピタルフライト』が起きかねません。・・・2000兆円と言われる個人金融資産が海外に向かってしまうことが危惧されます。これによって円の信認が失われ、大変な円安になることが一番怖い」(財界2024年2月14日号より)