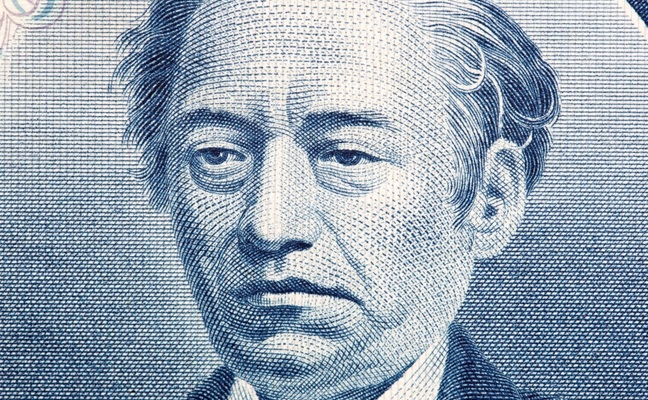慶応三年(1867)十二月八日から九日にかけて明治天皇隣席に下、朝廷内の小御所で慶喜の辞官納地と王政復古の大号令につき議論が交わされました。慶喜に辞官納地を求める岩倉たち討幕派の主張に親幕府の公家、大名たちは猛反発し議論は紛糾しました。何としても親幕派を論破しようと岩倉は奮闘します。
白熱した議論が飛び交う中、土佐の前藩主山内容堂が言った、「幼い天子を擁して数人の公家が天下を盗もうとしている」という発言を岩倉は無礼だとして威嚇し、容堂を言い負かしました。と、いう俗説がありますが、これは真実ではないようです。そのエピソードはともかく、議論百出の後、どうにか慶喜の辞官納地が決定されました。
岩倉たち討幕派の勝利と思いきや、慶喜は辞官納地を即座に実行すれば幕臣たちが騒ぐという理由で猶予を願います。討幕派は強気に即時実施を迫ろうとしましたが、京都には会津藩、桑名藩など親幕府の諸藩の軍勢が駐屯しており、戦を避けるべきという意見が討幕派の公家から上がります。
岩倉も弱気になり、慶喜が、「前内府」を名乗り、辞官納地に応じれば新政府の議定に迎えると妥協を考えます。慶喜はというと強気の姿勢を崩さず大坂城で英、仏、蘭、米、伊、普六カ国の公使を引見、王政復古後も自分が政府を代表するとアピールしました。
辞官納地は骨抜きとなり、慶喜は復権、討幕派は武力討幕の名目を失いました。そこで西郷は幕府から戦を仕掛けかけせようと幕府を挑発します。江戸で放火、略奪、殺人などを起こさせ、まんまとこの挑発に乗った庄内藩が薩摩藩邸を焼き討ちしました。この報せは大坂城にもたらされ、城内は薩摩討つべしの意見が沸騰、翌年の正月三日、京都に向け進軍しました。西郷にすればしてやったりですが、いざ、戦となりますと幕府は数で勝っています。いくら、最新式の軍備を整える薩摩長州といえど、勝利するとは限りません。いみじくも、「勝てば官軍、負ければ賊軍」と西郷が言ったように初戦の勝敗が討幕の成否を決するのです。