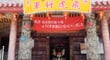ネット上をはじめ、あらゆるところで賛否両論飛び交う事態となっているパリ五輪の開幕式。否定的な意見も多々見られるのが現状ですが、京都大学大学院教授の藤井聡さんは、フィナーレを飾ったセリーヌ・ディオンによる『愛の讃歌』の歌唱に感動すら覚えたといいます。藤井さんはメルマガ『藤井聡・クライテリオン編集長日記 ~日常風景から語る政治・経済・社会・文化論~』で今回、その理由を詳しく記すとともに、3年前の東京五輪の開幕式に屈辱を感じた訳を綴っています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:【パリ五輪開幕式雑感】エッフェル塔でのセリーヌディオン「愛の賛歌」で閉じられた開幕式.日本の東京五輪開幕式を思い起こし、「令和日本」との間に文字通り大人と子供の差以上の開きを思い知り、屈辱を感ず
パリ五輪『愛の讃歌』の凄まじさ。思い出さざるを得ない、世界に「幼児のような三流国」と知らしめた東京五輪の開幕式
当方、五輪なるもの下品な商業主義に席巻された下らないグローバリズムイベントにどうしても見えてしまうので、さして心躍ることはないのですが、開幕式にはいつも、興味関心を持っています。
その国の国力を推し量るのに、とてもよい実験的イベントになっているからです。
どんな国でも、世界中が注目する五輪の開幕式となれば、恥ずかしくないそれなりのイベントに仕立て上げなければなりません。巫山戯(ふざけ)たものやセンスのない下らないことをやってしまえば、外国から侮蔑されてしまうからです。
だから、五輪開催国は国の総力を挙げて「こうすれば外国からセンスがないとは思われないだろうし巫山戯たものだと思われず、おそらくはセンスがあると思われ、一定の尊崇の念を集めることができるのではないか?」と、世界中の人々の評価を「忖度」してイベントをくみ上げるわけです。
だから、その国の五輪開幕式を見れば、その国の美意識やセンスがハッキリ見て取れるわけです。
とはいえ無論、これがいいだのアレがダメだのとの議論は百科騒乱となり、なかなか一つに纏めるのは難しい筈。ですが、そんな多様な意見をどうやって纏めて、一つのイベントを作り上げていくか…ということもまた、その国の力量を推し量る上で重要な要素となります。
ですから、その国の五輪開幕式は、第一に、その国のその時点における一般的国民の美意識・センスのレベルを暗示する重要な情報源であると同時に、第二に、その国がどの程度成熟した実務的実践能力(これは行政能力・実務的政治能力と等価の物です!)があるかを暗示する重要な情報源となるわけです。
はたして今回のパリ五輪はどうだったかというと、少なくとも色んな記事を見てると、ダラダラしたイベントだったとか、LGBTアピールが強すぎるだとか、韓国の紹介が間違えていただとか、アンチ・クリスチャン的要素が最悪だったとかいろんな批判が出ている様子。
このあたりの批判は、フランス革命によってアンシャンレジームを破壊した革命の影響で、フランスも随分と出鱈目な国になったということを指し示すものなのだろう…とは思いますが、当方が唯一目にし、そして、心底感動したのが開幕式のエンディングに登場したセリーヌ・ディオンの『愛の賛歌』の熱唱シーン。
当方、セリーヌ・ディオンという歌手は、そもそもあまり好きな歌手ではありませんでした。自分の歌唱力の高さを鼻にかけているところがあり、ポップシンガーとしてさして好きではありませんでしたが、今回の熱唱には、感涙むせび泣くほどの感動を覚えました。
まだご覧になっていない方は是非、下記よりご覧になってみて下さい。
この記事の著者・藤井聡さんを応援しよう