9連休という年末年始の長期休暇も終わり、今年もついに仕事や学校が始まった方が多いことでしょう。長い休みが明けると、仕事や勉強へのモチベーションを上げるのも大変。そこで今回は、メルマガ『久米信行(裏)ゼミ「大人の学び道楽」』の著者である久米信行さんが「勉強をしない息子にやる気を出させたい」というお悩みへどのように回答したのかご紹介します。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:勉強をしない息子への接し方
オトナの放課後相談室:勉強をしない息子への接し方
Question
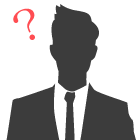
小6の息子が勉強しなくて困っています。家ではゲームとスマホに明け暮れて、週末は少年野球に明け暮れて、勉強をしている素振りがありません。よくひどい点のテストを持って返ってきます。小学校の勉強でつまずくと、中学、高校も苦労すると思うと、何とか勉強をする習慣を身に付けさせたいと思っています。
本人に煙たがられずに、その気にさせる良い方法はないでしょうか。
(東京都/42歳/男性)
久米さんからの回答
親子で在宅リスキリングに挑戦して学ぶ楽しさを共有されてはいかがでしょう。できれば息子さんの方が得意になり、逆に教われるようなITネタを選んで。
これは難しいご相談をいただきました。なぜなら、大学で教えている私が言うのも何ですが、苦労して受験に合格し、大学でテストをクリアするためにしてきた暗記中心の勉強は、これからほとんど役に立たなくなるからです。
その理由は、検索窓に何か問いかけをしたら、即座に回答してくる発展途上AIの能力を見れば明らかでしょう。
受験勉強をして、いい学校に入って、いい会社に就職してしまえば幸せ、、、みたいな時代は、終わりつつあるのです。
とはいえ、新しいタイプの生涯学習が親子ともども必要になることは間違いありませんので、その視点でお答えさせていただきます。
何か熱中できることがあるオタクこそ重要
まずは、ご令息が、スマホやゲームにせよ、少年野球にせよ、それに明け暮れるほど熱中できるものがあることを喜びましょう。
これまで20年近く大学で教えてきましたが、誰かに話しだしたら止まらなくなるような好きな物事があるバカモノ=好い意味のオタク=こそが日本の宝だと考えております。
好きな物事を、毎週1つずつ記事にせよという授業を行ったら、100人受講した学生が1年後には10人前後に減ってしまったことは、私にとって衝撃でした。受験に代表される暗記型の勉強はよくできるけれど、好きな物事を主体的に見つけ、それを独自のやり方で突き詰めていくことができない学生が大半だったのです。
つまり、息子さんには「よりよくありたい」という熱中気質・体質が備わっているのです。勉強しない子ではなく「選ばれし民」だと刮目しましょう。
子供に熱中させたいことにまず親が熱中する
子供は、親が楽しそうにしていることに、少なからず興味を持つものです。ましてや、ゲームやスマホを触っているということはデジタルネイティブなので、パソコンを使って親が楽しんでいることに興味を持つはずです。
イマドキの大学生は、スマホしか使えず、パソコンが使えないことも珍しくありません。
そこで、まず、父親としては、家でスマホを触るのはやめましょう。それよりもパソコンで楽しそうに仕事や学びをしている背中を見せるのです。
たとえ、疲れていても、食卓で、食事の前後に食卓で、なんだか楽しそうにパソコンの画面に向かい、キーボードをタッチタイプ=ブラインドタッチで打っている姿を見せつけてみましょう(タッチタイプができなかったら、この際親子で練習しましょう)。
「何を楽しそうにやっているのだろう」と、子供の方からのぞき込むようになったらしめたものです。
親が生涯新しい勉強を楽しく続ける姿勢を見せる
パソコンで見せつけるのは、会社からの持ち帰り仕事ではありません。それらは子供が寝てから片付けることにして、子供の前では、eラーニングで、何か新しい勉強をしているところを見せましょう。
父親世代も、これからは生涯学習、リスキリングをしなければ、生き残れない厳しい時代になります。実は、子供の心配などしている暇さえないのです。ですから、子供のやる気向上を兼ねて、自己投資のリスキリングを始める良いチャンスです。
「お父さん、何をやっているの?」
「プログラミングやAI活用の勉強だよ」
「え?大人になっても勉強ってするの?」
「これからは大人も勉強し続けないと時代についていけないんだ」
「それは大変だね」
「いや新しいことを学ぶのは楽しいよ。もっと学校でやっておけばと後悔してる」
「学校に行かなくても勉強できるの?」
「今はこうしてパソコンでeラーニングで学べるよ」
ああ、楽しいと、嬉々としてパソコンに向かう父の姿は、仕事で疲れてだらけて寝転び、テレビやスマホを漫然と見る父の姿と大違い。
きっと、子供が父親を見る目も変わるでしょうし、自分もやってみたいと思うのではないでしょうか?
この記事の著者・久米信行さんのメルマガ









