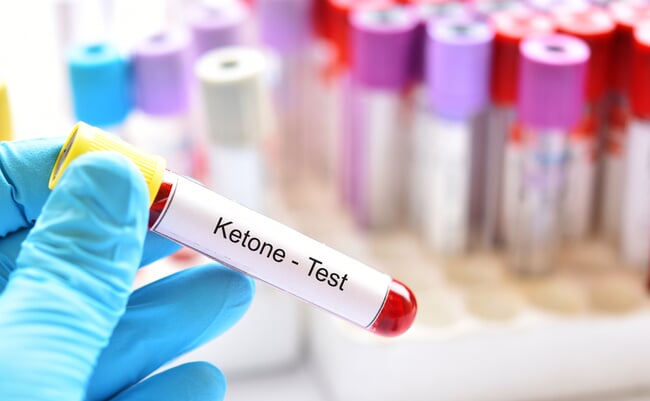体内の糖分が不足したときに生成され代替エネルギーとなる「ケトン体」は、体にさまざまな悪影響を及ぼすと、ほとんどの医者に悪者扱いをされてきたようです。しかし、そんなケトン体に腎臓を保護する働きがあると滋賀医大の研究チームが証明しました。2020年の新聞報道を元に解説するのは、メルマガ『糖尿病・ダイエットに!ドクター江部の糖質オフ!健康ライフ』著者で、糖質制限食の提唱者として知られる糖尿病専門医の江部康二医師です。江部先生は、ケトン体を「糖尿病急性合併症の原因物質」と断定している記事の間違いを指摘したうえで、滋賀医大チームの研究のあらましを伝えています。
医師に忌み嫌われてきた「ケトン体」、腎臓障害を予防する働きがあると発表
● 「ケトン体」が腎臓病を予防 糖尿病急性合併症の原因物質 安全な濃度究明へ 滋賀医大チーム /滋賀毎日新聞2020年7月29日 地方版滋賀県
2020年、毎日新聞朝刊に、上記記事が掲載されました。「ケトン体が糖尿病急性合併症の原因物質」とこの記事では断定していますが、これは、勘違いです。インスリン作用があるていど確保されていれば、糖尿病急性合併症(糖尿病ケトアシドーシス)は起こりません。
<糖尿病ケトアシドーシスの発症機序>
インスリン作用の不足→拮抗ホルモンの過剰→全身の代謝障害→糖利用の低下・脂肪分解の亢進→高血糖・高遊離脂肪酸血症→ケトン体の産生亢進→ケトアシドーシス
即ち、ケトン体高値は、糖尿病ケトアシドーシスの始まり(原因)ではなく、あくまでも結果なのです。インスリン作用が確保されていれば、血中総ケトン体(基準値28-120μmol/L)が4000-6000になっても、ケトアシドーシスにはなりません。
例えば、小児難治性てんかんの治療食である「ケトン食」を実践すると、血中ケトン体値は4000-6000に上昇しケトーシスを呈しますが、インスリン作用が確保されているのでアシドーシスにはなりません。インスリン作用が保たれている限り、ケトン体が上昇してもそれは、生理的ケトーシスであり、問題はないのです。
ともあれ、日本では長い間、悪者扱いされ、ほとんどの医師に忌み嫌われてきたケトン体が、腎臓障害を予防する働きがあると発表された滋賀医大チーム、good jobです。ケトン体大好きな私としては、嬉しい限りです。
【記事内容の要約】
滋賀医科大の前川聡教授(糖尿病内分泌・腎臓内科)は「(腎臓への障害が進むと必要になる)人工透析治療の導入を減らすことにつながる、画期的な発見」と期待しておられます。
7月28日付の米科学誌「セル・メタボリズム」電子版に論文が掲載されました。セルメタボリズムはインパクトファクター15.95と信頼度の高い学術雑誌です。
研究チームは、腎臓からブドウ糖を排出して血糖値を低下させる糖尿病治療薬「SGLT2阻害薬」が、患者のケトン体濃度を高めながら、強い腎臓保護効果があることに着目しました。
マウスを使った実験で、ケトン体が不足すると腎臓病の原因となり、適切な濃度のケトン体供給が腎臓保護につながることを、世界で初めて証明しました。
更に、糖尿病性腎臓病を引き起こす原因の一つ、たんぱく質「mTORC1(エムトークワン)」の暴走についても、ケトン体が抑制することを発見しました。
前川教授は「今後はヒトに近いカニクイザルで検証し、腎臓保護に有効かつ安全なケトン体濃度を見いだしていきたい」と話されました。
この記事の著者・江部康二さんのメルマガ
image by: shutterstock.com