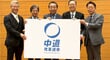だが、アンドリー氏の疑念も尤もと思えるほど、鈴木氏のロシア寄りの発言は度を越している。
たとえば、3月24日の現代ビジネスに掲載された田原総一朗氏との対談記事。
鈴木 「2021年10月23日、ゼレンスキーはウクライナ東部に自爆ドローン(無人攻撃機)を飛ばしました。プーチンさんはビックリして、ただちに10万人の兵をウクライナ国境に配備したわけです。ゼレンスキーがドローンなんか飛ばしてロシアを挑発していなければ、そもそもこんな騒ぎにはなりませんでしたよ」
プーチン氏は「プーチンさん」、ゼレンスキー大統領のことは「ゼレンスキー」と呼び捨てなのが、自分の感情に素直な鈴木氏らしく、わかりやすい。
憤懣の矛先は岸田首相にも向けられる。
鈴木 「3月1日、日本はプーチンさんの個人資産を凍結する制裁措置を決めました。これは岸田首相が『我が国はプーチン大統領とは付き合いません』と宣言したに等しい措置です。日本のほうから『お前とはつきあわん』というカードを切るべきではありませんでした。こんなことをすれば、これからの北方領土交渉も平和条約交渉もありません」
鈴木氏の言う通り、ロシアは日本を「非友好的な国・地域」に指定し、北方領土交渉の中断を通告してきた。
むろん、岸田首相としては、そうなることを承知のうえでの苦渋の決断だった。4月4日付の朝日新聞に、岸田首相が結論を出すまでの経緯が描かれている。
日本政府は今回、米欧の求めに応じ、ロシア政府関係者の資産凍結など、原則足並みを合わせる方針をとっていた。ただ、プーチン氏への制裁は次元が異なり、外務省や自民党内には慎重論が根強くあった。首相は逡巡した。(中略)首相は、外務省幹部らと複数回にわたって協議。「腹をくくるかどうか」と自らに語るように繰り返し、最終的にこう伝えた。「G7と足並みをそろえる。中途半端なことをやってどう評価されるか考えたら、もうやるしかない」
首相は、安倍晋三元首相の携帯電話を鳴らした。北方領土交渉を「戦後日本外交の総決算」とアピールした安倍氏への「仁義」だった。首相の判断を、安倍氏も受け入れたという。
安倍親露外交との決別。それは、岸田首相にとっては、外交の主導権を官邸から外務省に戻すという選択である。
安倍時代の官邸外交について、朝日の同記事はこのように書いている。
主導したのは、経済産業省出身者を中心とする官邸官僚。「外務省にはアイデアがない」と言い放ち、共同経済活動などの経済協力を推し進めた。外相の岸田氏と外務省は蚊帳の外に置かれた。
あくまで、官邸と外務省という組織の対立図式でとらえている。一方、アンドリー氏は著書『プーチン幻想』のなかで、安倍氏の属人的問題としてその親露姿勢を分析してみせた。
安倍氏自身にプーチン幻想、自信過剰、実績欲しさがあること。そして、安倍氏に影響を与えた人々がいることを指摘する。
安倍総理の周りにいる日本の親露派の影響である。某元首相や某地域政党代表を始めとする親露利権屋は、総理大臣に対露接近を強く勧めている。彼らは日本がロシアと関わりが深くなることによって、自分が金儲けできると思っている(あるいはロシアに思わされている)ので、総理にロシアと接近することがいかによいことか、と説得していることが想像できる。そして真に残念なことに、安倍総理は彼らの話を真に受け、勧められたとおりにしている。
某元首相は森喜朗氏、某地域政党代表はもちろん鈴木宗男氏のことを指すのだろう。維新の音喜多氏は、鈴木氏のためにアンドリー氏を問い詰めようとして、逆襲されたというところか。
国家権力と偏向メディアの歪みに挑む社会派、新 恭さんのメルマガ詳細・ご登録はコチラ