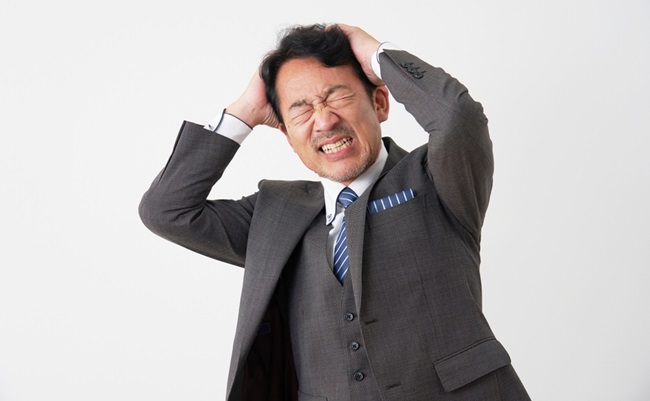採用した社員が、実は能力不足だったので減給や解雇も考えている──。そんなお悩みが無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんのもとに届きました。果たして法的に解雇等は可能なのでしょうか?
能力不足の労働者への対応
採用した従業員が何度、注意や指導しても同じミスを繰り返し、まったく改まらないとの相談を受けました。会社としては、能力に見合う賃金額への変更や、場合によっては辞めてもらうことも考えているとのこと。
賃金の減額変更については、原則、当事者の合意が必要です。雇用契約も“契約”である以上、その契約内容を変更するには当事者の合意が必要となります。
ただし、雇用については、雇用契約書だけでなく、会社の就業規則や賃金規程等も雇用契約の一部と考えられるので、就業規則等の規定を根拠に契約内容を変更することも可能です。この場合には、その変更が、“会社による権利の濫用”に該当しない限り、変更が有効になります。
そして、“権利の濫用”とならないためには、“変更の合理性”が必要です。今回の件でいえば、労働者の能力不足および改善がみられないこと、そして、その能力に見合う賃金額がいくらになるかを如何に客観的に証明していくかが重要になります。
次に、辞めてもらう場合ですが、退職勧奨もあれば解雇もあり得ます。退職勧奨とは、「辞めてくれないかなあ」という、会社から労働者への退職の提案です。
これに対し、労働者は自由な意思で、応じるかどうかを決めることになります。ですから、退職勧奨を行っても、必ず労働者が辞めるわけではありません。
解雇については、会社からの一方的な雇用契約の解除ですので、労働者が同意するかに関係なく、解雇は有効になります。
ただし、“客観的に合理的な理由”と“社会的な相当性“がない解雇は、権利の濫用として無効となるので、安易な解雇は避けるべきです。
そこで今回の場合、教育指導をしっかり行い、それでも能力向上がみられず、他部署への異動も難しく、これ以上、雇用契約を継続することが難しいといった状況が必要でしょう。
「何でそこまで!?」と思うかもしれませんが、日本では、解雇がそれほど難しいのです。ただし、解雇無効を判断するのは、あくまで裁判であり、裁判で無効との判決が確定するまでは、解雇は有効と考えられます。
以上の考え方を参考に、会社としてそれぞれのリスクを評価し、どのような対応をしていくかを判断していただくことになります。残念ながら、万能の対応方法などありません。
image by: Shutterstock.com