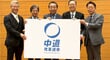『縮みゆく女』のストーリーは以下のように要約できます。
「とある主婦がどんどん縮んでいってしまう」おしまい。というか、もともと『縮みゆく人間』がそういう話なのでパロディ版『縮みゆく女』も基本的には「主人公がどんどん縮んでいってしまう」以上のことはないのですが、たとえば『縮みゆく人間』には話の途中で、ものすごく小さくなった主人公が箱の中に落ちてしまう場面があります。旦那を見つけられなくなった奥さんは彼を死んだものと思ってしまうのですが、これをそっくり模した場面が『縮みゆく女』にもあり、実はしっかりとオリジナルに敬意を表した作品となっています。
『縮みゆく人間』には(自分のサイズからみると)巨大なモンスターと化した猫に対面してガーンという場面もありますが、『縮みゆく女』では危ないのでペットの犬を家族がよそに預けたりもしています。オリジナル版の『縮みゆく人間』は、性的に不能になり、社会の中での役割がどんどん縮小されていってしまう「男」の恐怖をメタファー的に描いた作品だとされています。そういう社会的な、あるいは実存的な恐怖を文字通り、自分が小さくなってしまうことでうまく表現しているわけです。
では『縮みゆく女』はどうでしょうか。これもまた、時代背景と結びついています。
リリー・トムリンが演じる主人公は絵に描いたような単なる主婦で、その名をパット・クレイマーといいます。この「クレイマー」という苗字はもちろん、映画『クレイマー、クレイマー』から来ています。『クレイマー、クレイマー』は、おさんどんと育児だけを押し付けられたクレイマーさんちの奥さんが「自立して仕事をしたい!」と家を飛び出たことから話がスタートするのですが、『縮みゆく女』のパットは旧来の「主婦」というポジションになんの疑問も抱いていないので、当時の女性解放運動の高まりを考えるとある意味「時代遅れ」の女なのです(そんな彼女の苗字が「クレイマー」というのが既にギャグだというわけです)。
旦那さんや二人の子供とパットが暮らすのは、まんま絵に描いたような郊外の住宅です。1950年代、アメリカの白人はどんどんと郊外の住宅地に移動しました。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では、50年代に郊外のニュータウンが作られていくさまと、それが完全に定着した80年代を対比させていました。80年代はいろんな意味で50年代のリバイバルだったので、この対比は鮮やかなものでした。
『縮みゆく女』でパットが住む郊外の町並みは、すべてがパステルカラーに彩られた、まるで50年代のカタログのような絵空事の世界です。50年代といえばパステルカラーとネオンと市松模様なわけですが、こういう「パステルカラーの50年代」の「郊外」を同じように戯画化してみせた作品にはティム・バートンの『シザーハンズ』や、『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』(の中の、オードリーの郊外幻想の場面)などがあります。『縮みゆく女』はそういった郊外の町並みをはじめ、衣装や家具に至るまで、このパステルカラーの色彩設計が徹底されていて素晴らしいのですが、ここに監督ジョエル・シュマッカーのファッション・センスが反映されているのは間違いないところでしょう。
しかし『縮みゆく女』のパステルカラーの郊外が、50年代とはっきり違う点がひとつあります。それが広告です。もちろん50年代も広告の時代ではあるのですが、『縮みゆく女』の世界では、近所の人たちがみなキャッチフレーズを口ずさみながら芝刈りをしたりバーベキューをしたり車を磨いたりしていて(つまり、彼らの行動自体がそれぞれ芝刈り機やバーベキューセットや車用洗剤の宣伝になっている)、さらにテレビからも怒涛の勢いで洗剤やシャンプーやスプレーや糊の宣伝が垂れ流されているのです。これはちょっと悪夢的で面白い演出ですが、のちにわかるように、そうやって宣伝されている化学物質たっぷりのあれこれを併用した結果の副作用として、パットはどんどん縮んでいくことになったのです。これもやはり当時、食品や洗剤に含まれる化学物質が大きな社会問題になっていたことと関係しています。