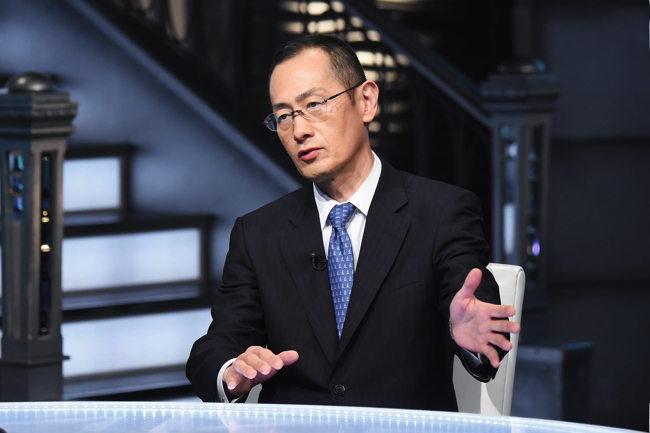
巨大ビジネスも始動~山中はなぜスピードにこだわるのか
そんなiPS細胞に巨大ビジネスも動き始めていた。売上げ1兆8千億円の武田薬品工業。神奈川県藤沢市にある湘南研究所は1000人の研究者が集結する、新薬開発の中枢だ。そこに山中は毎月通い詰めているという。実は山中は2年前から武田と共同で研究を行なっている。
今、iPS細胞を巡って大手製薬会社は巨額の投資をし、熾烈な新薬の開発合戦を繰り広げている。武田はiPSの主役、山中を招くことでその覇権を握ろうと考えているのだ。
一方の山中はここまで深く大手と手を組んだ理由を「製薬会社の研究の本拠地に入れていただいてチームを作ってできるということは、ここにあるすべてのリソースにアクセスできるということ。思っていた以上に効率がいい。やってよかったと思います」と、語る。
薬の開発になぜiPS細胞が重要なのか。ここではiPSの技術を使って、筋ジストロフィーの患者の細胞を増やしているという。筋ジストロフィーは、筋肉細胞が破壊されていき、最悪の場合死にいたる遺伝性の難病だ。そんな難病にかかっている患者の細胞をiPS技術で初期化し、筋肉細胞に変化させると、作られた細胞には病気の症状が現れる。病気にかかった細胞を再現できることで、薬の効果を驚異的なスピードで確認できるようになったのだ。
武田薬品工業の佐々勝則さんは「iPS細胞を使うことで、病気の状態を試験管レベルで再現できるようになった。iPS細胞だからこそできる技術で、大きく変わったと思います」と、語る。
大手メーカーと組んでまでスピードにこだわる山中。そこには1秒もムダにできないという強い思いがあった。
去年亡くなった日本ラグビーのトッププレイヤー、平尾誠二さん。その感謝の集いで、生前、親交があった山中は「治すことができなくてごめんなさい」と胸の内を語った。ノーベル賞以来、山中は自らに問いかけ続けている。「まだ一人の患者も救えていない」と。
山中の拠点は京都にある。鴨川の畔にある京都大学医学部付属病院。敷地の中心にそびえる真新しい巨大な建物が、総工費100億円を投じたiPS細胞研究所だ。
その所長を務める山中の一日は、まさに分刻みの忙しさ。同時進行する様々なiPS研究を進めながら、所長として研究資金集めにも奔走する。
「日本の普通の大学では教授ごとに部屋が区切られていて、隣の研究室が何をしているのかわからない」(山中)というが、この施設は、研究成果を素早く共有するための大部屋方式。何よりもこだわるのはやはりスピードだ。
「患者さんはどんどん悪くなっていくわけですから、時間との戦い。今までの研究とは比べものにならないプレッシャーもあります。いかに医療現場に届けるかが研究所全体の目標ですので」(山中)
手術が下手な“ジャマナカくん”がノーベル賞を受賞するまで
1962年、山中は東大阪の町工場の家に生まれた。父親からは「お前は経営者に向かない、医者になれ」と言われて育った。
父の言葉に従い神戸大学医学部へ。スポーツに打ち込んだ山中は10回以上も骨折。そんな中で世話になった整形外科医に憧れ、自分も目指すことに決める。
国立大阪病院で整形外科医として研修を始めた山中。ところが意気揚々と挑んだ最初の手術は、普通なら30分ほどで行う簡単なものだったのだが、2時間かけても終わらない。そしてついたあだ名が「ジャマナカ」だった。
「患者さんは1回限りの勝負ですから、自分は緊張に弱いんだな、と」(山中)
自分は医者に向かないのではないか。そんなことを考え始めた頃、長年、肝硬変で病床にあった父がなくなった。山中は整形外科医をやめ、難病を治すための研究に取り組む決意をする。1989年、大阪市立大学大学院薬理学教室に入学。長い基礎研究の闘いが始まった。
アメリカ・サンフランシスコ市内に山中のもうひとつの研究拠点がある。グラッドストーン研究所。現在も一研究者としてここでiPS細胞に関する基礎研究を続けている。ここは山中が31歳の時、初めてアメリカに渡り研究を始めた場所だ。
「アメリカには思い入れがあった。これまでやっていない新しいことをやりたかったので、アメリカに何十と手紙を書いて、研究員に応募したのを覚えています。ほとんど返事は来なかったけど、最初に返事をくれたのがグラッドストーン研究所。うれしくてすぐに行くことにしました」(山中)
ここで山中の人生を変える出会いがあった。その相手とは当時、研究所長だったロバート・メーリーさん。メーリーさんは自分の愛車、フォルクスワーゲンの頭文字「V・W」にたとえて、山中にこんな話をした。
「学者として成功するためにはVとWが最も重要だと教えました。VはビジョンのV、そしてWはワークハード。つまり、がむしゃらに働くだけじゃなく、ビジョンがなければいけないということです」
山中はこの話を聞き、初心に返る。
「当時はいい実験をして、いい論文を書いて、研究費をもらって、いいポストに就くというのが目標みたいになっていた。しかしよく考えると、それはビジョンではない。やはり臨床医のときに治せなかったたくさんの患者さんを、自分の父親を含めて、何とかしたい。そういう思いで研究者になったことを思い出して、それが自分のビジョンだ、と」(山中)
3年の研究を終え、山中は帰国する。しかしそこで山中を待っていたのは、厳しい現実だった。当時の山中を知る大阪市立大学の三浦克之教授は「アメリカの環境があまりによすぎる。日本の環境はそれにともなっていない。泣きそうになっているのも見ています」と言う。
アメリカなら専門の職員が世話をしてくれていた実験用マウス。その餌やりから掃除まで、全てが山中の仕事だった。そんな厳しい雑務に追われる中、すでにテーマと決めていた細胞の初期化の研究は一向に進まず、山中は鬱状態にまでなってしまう。
そんな山中を元気づけたのが、クローン羊・ドリーの誕生だった。成長した羊の一部の細胞から羊丸ごとのクローンを作れるという事実が、iPS細胞も夢ではないと確信させたのだ。
そして、奈良、京都と研究の拠点を変え、執念深く実験に明け暮れた山中を支えたのは、難病に悩む患者を助けたいという、揺らぐことのないビジョンだった。
気の遠くなるような実験を繰り返す中、ついに山中のチームは見つけ出す。山中は培養器の中で、世界で始めて細胞を初期化するために必要な4つの遺伝子を特定した。
父を亡くし、基礎医学の道に足を踏み入れてから17年目のことだった。










