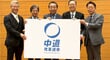緊迫度を増すウクライナ情勢の打開を図ろうと、年明け早々の10日にアメリカ、12日にNATO、13日にはOSCEがロシアと協議しましたが、いずれも不調に終わってしまったようです。この状況に「決裂」という決定的な表現を選択するのは、ロシアの軍事・安全保障政策が専門の軍事評論家・小泉悠さんです。今回のメルマガ『小泉悠と読む軍事大国ロシアの世界戦略』では、着々と集結するロシア軍の動きからウクライナへの侵攻準備が整いつつあると警告。核を限定的に使用するオプションまであると分析しています。
ロシアという国を読み解くヒントを提供する小泉悠さんのメルマガ詳細・ご登録はコチラ
西側との対話決裂 考えられるオプション
あけましておめでとうございます、というにはもう年が明けてからだいぶ時間が経ってしまいました。とはいえ、まだ新年に入ってから2週間少しだというのに、今年ももう随分と盛り沢山な感じです。
カザフスタンにおける突如の騒擾発生とこれに対する集団安全保障条約機構(CSTO)による平和維持部隊の派遣、そしてこの間に起きたトカエフ大統領によるナザルバエフ元大統領排除の動き(と思われるもの)はその第一に数えられるでしょう。第二に、北朝鮮が極超音速ミサイルと自称する新型ミサイルを立て続けに発射し、どうやら実際にある程度の軌道変更能力を持っているらしいことがわかってきました。
これらの出来事については次回にでも詳しく扱いたいと思いますが、今回は第三の出来事、すなわちウクライナをめぐるロシアと西側の関係性について引き続き考えてみたいと思います。
失敗に終わった対話
先週、ロシアと西側諸国の間では一連の対話が行われました。最初に行われたのは、1月10日の米露外務次官級協議です。米国のシャーマン国務副長官とロシアのリャプコフ外務次官を筆頭とする両国外交団はスイスのジュネーヴで会合し、昨年12月にロシア外務省が提示した新たな欧州安全保障枠組みに関する条約案について8時間にわたる話し合いを持ったとされています。
ロシア外務省のサイトに掲載された条約案を見ると、
- 米国はNATOを旧ソ連諸国に拡大させようとしないこと(第4条)
- 米露は既に配備されたものを除いて同盟国に新たな部隊配備を行わないこと(第5条)
- 互いの領土に届く範囲に短・中距離攻撃兵器を配備しないこと(第6条)
- 国外に核兵器を配備しないこと(第7条)
などが謳われており、一種の不可侵条約を目指したものであることがわかります。
しかし、協議後、シャーマン副長官はNATO不拡大案は受け入れられないとして上で、ロシアがウクライナへの軍事圧力を緩和しないことには「建設的で生産的な外交を行うことは非常に困難だと伝えた」ことを明らかにしました。
● ウクライナ情勢でアメリカとロシアの高官が協議 隔たり大きく | NHKニュース
続く12日には、ロシアがNATOに対して提案した類似の条約案(本メルマガ第158号を参照についての協議が行われましが、その結果はやはり大同小異でした。
ロシアという国を読み解くヒントを提供する小泉悠さんのメルマガ詳細・ご登録はコチラ