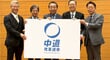「一緒に暮らす」と「子供をもつ」という2軸が大事
日本の結婚に関する法律を調べた結果、
・ 一緒に暮らすこと
・ 子供を持つこと
の2軸を中心に法律が書かれていることに気がついた。
この2軸をおさえておくと、結婚におけるお金の損得を計算できるようになる。では、この2軸について順に説明しよう。
一緒にくらすこと
同棲かの区別が難しいが、基本的に男女が一緒に暮らすと「内縁」と呼ばれる状態になる。内縁には事実婚と結婚の両方が含まれる。内縁になると「利益の山分け」というルールが生じるようになる。婚姻費用や財産分与など細かい規定があるが、要するに「一緒に暮らしている男女は仲良く利益を山分けしなさい」といっているに過ぎない。
山分けの意味を理解していただくため、一つ例をあげよう。
いま、A君とBさんが一緒に暮らし内縁関係になったとしよう。そして、
・A君の年収:500万円、年間支出:500万円、利益:0万円
・Bさんの年収:1000万円、年間支出:200万円、利益:800万円
だとしよう(つまり、Bさんは優秀かつ倹約家であり、A君は浪費家というケースである)。
収入と支出は山分けなのでA君とBさんが内縁関係になると
・A君とBさんの年収和:1500万円、年間支出:700万円、利益:800万円
・A君の年収:750万円、年間支出:350万円、利益:400万円
・Bさんの年収:750万円、年間支出:350万円、利益:400万円
となる。
では結婚前後でA君とBさんの利益変化について計算する。
結婚前後での利益差を計算すればいいので、
・A君の利益差 = +400万円
・Bさんの利益差 = -400万円
となる。
わかっていただけただろうか。日本の法律では、内縁関係になると利益に変化が生じるのである。一緒に男女が暮らすだけで、利益を山分けしなくてはいけないのだ。
子供を持つこと
では2つ目の軸である「子供をもつこと」へ移ろう。子供をもつことで「養育費」というものが発生する。養育費は親が子供に対してもつ義務であり、離婚した後でも子供が大人になるまで支払い義務は続く。養育費の計算は少し複雑である。
面倒なのでざっくり「年収の10%ほど」と考えていい。細かい話になるが、養育費は親権を持つ親の年収が高いと少なくてすむ。逆に、親権を持たない親の年収が高いと、養育費は高くなる。
式にすると
(比例係数) x (親権を持つ親の年収) / ((親権を持つ親の年収) + (親権を持たない親の年収))
となる。
「差ではなく比で決まる」のが特徴である。そのため、いくら親権を持たない親の年収が高くても、
(比例係数) x (義務者の年収) / ((義務者の年収) + (権利者の年収)) = (比例係数)
と、比例係数(15%ほど)が上限となる。
ここで注意だが、認知がないと養育費がとれない。そのため、女性の場合、子供ができたら必ず認知をしてもらおう。