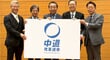「我慢は日本人の美徳」とされてきました。確かに事実である側面もありますが、必ずしもそれがグローバル化する社会で競争力につながっているとは言えません。渋沢栄一の子孫で、世界の金融の舞台で活躍する渋澤健さんは、ただ我慢させるだけでは優秀な人材がどんどん海外へ流出してしまうと危惧しています。
「我慢は美徳」とされる日本で失われてしまったもの
謹啓 新春のお慶びを申し上げます。
常に視界に靄がかかったような状態のウィズコロナ生活に慣れてきた感じがしますが、やはり今年はすっきりとした青天を望みたいものです。この二年間、特に大学進学や就職などの人生の新しいステージに入った若者たちが気の毒でした。オンライン事業やウェブ会議など、「デジタル」は機能として便利ですが、新たな人間関係をつくり、深めるには心身で体感できる「アナログ」な空間が大事です。
一方、どの時代でも「最近の」若者たちは、常に「最近の」新しい環境に適応する力があると思います。既存の固定概念から解かれているからこそ、過去でも現在でも、若者の存在が重要であり、彼らが活躍できる社会は活気ある社会になるのです。コロナ禍は若者たちにとって厳しい現実であったことに間違いはないですが、そこから生まれた果実もあったようです。つまり、「コロナ果」です。
「コロナ果」という言葉は、読売新聞元文化部長で早稲田大学文化構想学部教授の尾崎真理子さんが指導されている演習の学生たちが発案した表現です。就活の時期が3年生の秋まで早まった上にリモートで面接が進むなど、かなりの異変に戸惑う学生も少なくなかったようでした。
しかし、学生たちが提出した「ポストコロナの文化」レポートを拝読させていただいたところ、新しい時代への希望の兆しも読み取れます。
例えば、「コロナ『果』の演劇」という題名でレポートを提出した大学4年生は、「『コロナ禍だから』と後ろ向きになるのではなく、逆にコロナ禍だからこそできること、コロナ禍によって実ったものは何なのかを考えるきっかけになった」ようです。
他に、「無観客ライブ」や「バーチャル博物館」というコロナによる色々な新しい工夫を評価しつつ、「展示物のオーラ」は変わらないという指摘、あるいは、「劇場は地域社会における『ハコ』ではなく文化から生まれる対話の連なりの『場』」であると、むしろリアルな体感に対する感度が高まったことを示唆する学生たちもいました。
このように感性が豊かな学生たちでありますが、彼らは「日本企業にかなり失望」しているようです。
その理由を問うと、それは就活を通じて見えた日本企業の姿が、「型にはめられる」とか「賃金が安い」などというイメージがあるからだそうです。このような若者たちの懸念に、「彼らは若くて我慢できないから」と肩をすくめることしかできない企業は、新しい時代に乗り遅れるでしょう。
我慢は日本人の美徳であることは間違いありませんが、その我慢が日本企業の競争力につながったというエビデンスは、直近の数十年では乏しいのではないでしょうか。
忍耐強く努力することは、「型にはめる」ことや既存の固定概念に囚われることではなく、自身の道理に反して口をつぐむことでもありません。また、ただひたすら我慢するのではなく、その先には何らかの形での報いが必要でありましょう。