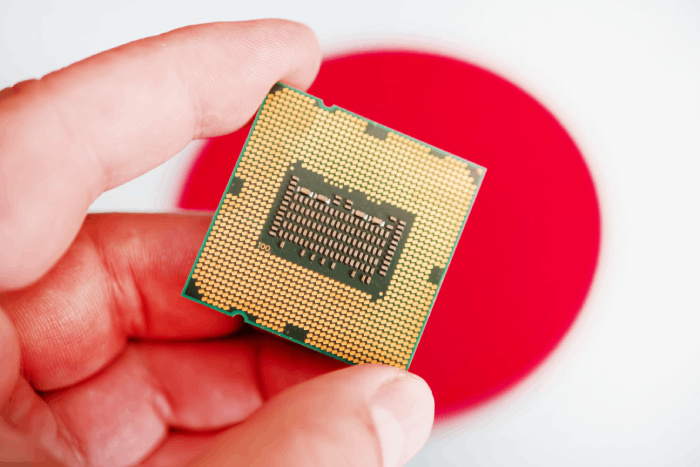日本の国策半導体ラピダスとカナダのテンストレントが共同で開発している「エッジAIアクセラレータ」は、2ナノ半導体技術を活用する生成AIを登載する。このプロジェクトは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」に採択された国策事業である。2027年までに開発を目指しており、研究開発は順調に進んでいる。肝心の「2ナノ半導体」製造のメドもついた。24年12月、「国際電子デバイス会議(IEDM)」で正式に公表されている。
ラピダスの「2ナノ半導体」開発は、未だに誤解・誤報・中傷が飛び交っている。TSMCやサムスンが開発できなかった、電気が微細な回路から漏れないように特定の層に絶縁膜をつくるSLR技術で成功したからだ。「40ナノ」しか製造しない日本半導体技術で、「2ナノ」(SLR技術採用)を開発するのは「逆立ち」現象としている。ただ、世界の半導体基礎技術は、1980年代の日本技術陣が開発構想を発表したものの延長に過ぎないのだ。日本には、潜在的に高い半導体開発能力がある。かつての王者であるからだ。
ラピダス歩留まり90%へ
米国エヌビディアは、生成AI半導体で世界において独走状態にある。製造は、TSMCが請負っているが、エヌビディアはラピダスの技術水準を評価しており、ジェンスン・フアンCEOは「ラピダスに製造を請負ってもらえれば栄誉」としている。ラピダスの技術が、海のものとも山のものともつかぬようなものであれば、こうした発言をするはずもないであろう。
ラピダスの小池淳義社長は、現在の開発状況を明確に発言している。製品コストの死命を制する製品歩留まり率が、1年以内に最大90%まで高められると強調している。「通常、歩留まり30%に達して生産を始めるまでに最大1年はかかる。しかし、ラピダスのスピードは極めて速いので、生産開始までに歩留まり50%へ簡単に行ける」と小池氏は見通しを語る。「1年以内に80~90%に達するのも可能」と極めて明るい見通しである。英紙『フィナンシャル・タイムズ』(24年12月4日付)が報じた。
現在、世界で生産されている最先端半導体は「5ナノ」が最高である。TSMCの歩留まり率は約70%とされるが、サムスンは20~30%で足踏みしている。TSMCは黒字だが、サムスンは大赤字に陥っている。これに対して、ラピダスは「2ナノ」で1年以内に80~90%の歩留まり率を実現可能としている。ラピダスが、半導体製造を全自動化したからこそ可能になったものだ。
米国IBMが、ラピダスへ「2ナノ」製法特許を供与するまでに紆余曲折を経た。IBMは当初、サムスンへ「5ナノ」製法特許を供与したが、前述のとおり歩留まり率20~30%の低空飛行である。これでは、ビジネスにならないとして、「40ナノ」しか製造していない日本へ打診した。IBMは、日本の高い半導体開発能力を熟知していたのだ。この切り替えは、見事に成功して「大輪」を咲かせる結果になった。IBMという「伯楽」は、日本という「名馬」を探り出したことになる。
ラピダスは、納期を6割短縮できるとしている。歩留まり率が最大90%まで高まれば、「短納期」が実現する。これによって、TSMCと十分に対抗できるとしている。小池社長は24年12月、オランダASMLの極端紫外線(EUV)露光装置をラピダス千歳工場へ搬入した。その際、搬入台数について明言しなかった。「1台や2台でない。複数である。台数を明らかにすれば、ラピダスの今後の生産計画が分かってしまう」と茶化したのだ。
これは、小池社長がこれまでに「千歳へ第二工場を作りたい」と発言していることと符節を合わせたものである。技術的には、ここまで見通しを持っていることが分る。だが、半導体のファンドリー(受託生産)で独占的地位にあるTSMC幹部は、ラピダス対して冷淡な見方だ。ラピダスは競争相手ではないと言う。「彼らは、ビジネスや収益を本当に目指しているのではなく、(起業を支援する)インキュベーターに近いように思える」(前記のFT記事)。
こういう否定的な情報が、日本国内を駆け巡っている。ラピダス反対派には「心地よく」聞こえるのであろう。このTSMC幹部の発言は、調子に乗りすぎている。TSMCは、筑波へ研究所を作り「2ナノ」半導体の素材開発で日本企業の協力を仰いでいるのだ。ここで得られた知見は、国策企業ラピダスへも流れている。研究助成金が、日本政府からも出ているからだ。TSMCのこうした奢りは、いずれ反省時期がくるであろう。
Next: 日本復活はすぐそこ。再び半導体大国へ