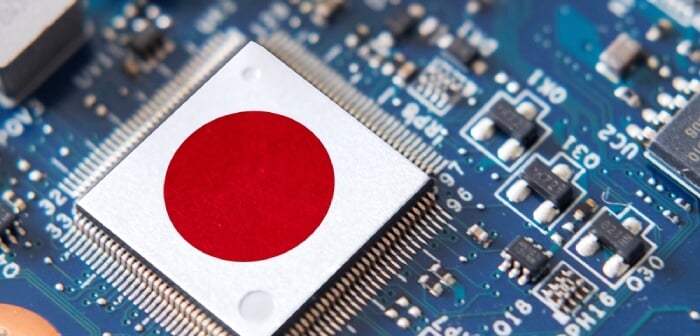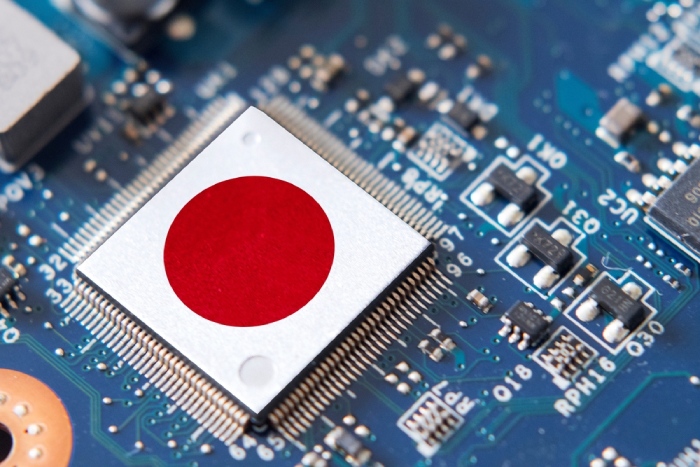日本の半導体産業が再び世界の舞台で輝きを取り戻そうとしている。国策半導体企業ラピダスは、IBMとの共同研究により「2ナノ」技術で世界初の成果を達成。これにより、技術的なリードを取り戻すだけでなく、日本国内外の企業や研究機関との連携を強化し、半導体分野での新たな地位を築きつつある。本記事では、ラピダスの技術力の実態と、それを取り巻く期待と批判について詳しく解説する。(『 勝又壽良の経済時評 勝又壽良の経済時評 』勝又壽良)
プロフィール:勝又壽良(かつまた ひさよし)
元『週刊東洋経済』編集長。静岡県出身。横浜市立大学商学部卒。経済学博士。1961年4月、東洋経済新報社編集局入社。週刊東洋経済編集長、取締役編集局長、主幹を経て退社。東海大学教養学部教授、教養学部長を歴任して独立。
日本半導体の未来は明るい
日本では半導体について、未だにトラウマにとらわれている人々が存在する。国策半導体企業ラピダスについて、悲観情報を流し続ける一群の人々だ。この特徴は、ラピダスの現実の技術開発過程に関する情報を把握せず、古い技術知識でラピダスを論評している。日本の半導体開発力を、驚くほど低評価しているのだ。「腐っても鯛」という言葉を忘れている。
こういう「誤解」を一掃するニュースが報じられた。米サンフランシスコで開催されている「国際電子デバイス会議(IEDM)」で12月9日、ラピダスとIBMが2ナノ半導体の研究成果を発表したのだ。対外的公表は、今回が初めてである。
2ナノ品のトランジスタ(半導体素子)は、GAA(ゲート・オール・アラウンド)と呼ばれる複雑な構造を使っている。電気が、微細な回路から漏れないように特定の層に絶縁膜をつくるSLR技術で成功した。これは、世界で初めての成果である。電圧を細かく制御でき、少ない電力で複雑な計算処理がこなせるようになった。
実際に技術開発を担ったのは、ラピダスの富田一行氏である。富田氏は、「ラピダスの北海道工場にこの技術を導入し、先端品の製造につなげる」とコメント。IBMは、「(2ナノチップの)厳しい技術要件を満たすことができた」とした。『日本経済新聞』(12月10日付)が報じた。
詳細な内容については後で取り上げるが、従来の古い2ナノチップ製造法のFinFETを上回り、TSMCやサムスンを技術的に追い抜いたのだ。日本は、再び半導体トップへ立てる希望を持てる段階へ到達した。意味もなく、トラウマに固執して卑下することは、余りにも非生産的な話である。
これは、ラピダスが最先端半導体製法で世界トップに踊り出たことを意味する。しかも、ラピダスは半導体製造過程の「前工程」と「後工程」の全自動化にも世界で初めて成功している。これによって、納期は66%も短縮化できる見通しまでついている。ラピダスの技術開発過程をつぶさに把握すれば、ラピダス批判は的外れであることが分るであろう。
技術を無視の謬見(びょうけん)横行
つい最近、驚くべき「ラピダス批判」が報じられた。筆者は、慶応大学大学院教授の小幡績氏である。「半導体のラピダスはこのままでは99.7%失敗する」(『東洋経済オンライン』11月17日付)としている。その根拠として、次の3点を上げている。
- 場所(北海道千歳市)が悪い。輸送コストもかかり、人材など半導体関連のリソースも少ない。半導体製造に向く水質でない
- 提携先がよくない。すでに勝ちが確定している企業ではない。ファウンドリー(受託製造企業)中心とするならば、提携先はすでに勝ち組となっているか、圧勝確定の相手でなくてはならない
- 戦略がはっきりしない。そもそも目的がはっきりしない。研究なのか、開発なのか、製造なのか。雇用なのか、地域開発なのか、日本経済成長なのか、それとも経済安全保障なのか
以上3点の批判について検討してみたい。