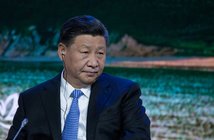アフリカにコカ・コーラを送り込むのが正式命令だった
興味深い話がある。
第二次世界大戦時、後にアメリカの第34代大統領となるドワイト・アイゼンハワーがまだ連合国の遠征軍最高司令官だった時、アフリカに遠征してまず何をしたのか。
1943年6月、アイゼンハワーは遠征軍最高司令官としてアメリカ政府に正式にこのような要求を突きつけた。
「コカ・コーラを300万本送れ。アフリカでコカ・コーラが生産できるように現地に工場を作れ」。
コカ・コーラ幹部はアメリカ政府と連合国軍最高司令官の「命令」に応え、当時のコカ・コーラの社長はこのように言った。
「どんなに赤字が嵩もうとも、アフリカにコカ・コーラを送り込んで価格もアメリカと同じにする」
コカ・コーラが買えるようになって、はじめて文明国になる
コカ・コーラはアメリカの兵士たちには必須の飲み物であり、これがないとアメリカ軍は「生きていけない」という認識だったのである。まさに、生命維持飲料の扱いだった。
アメリカ軍がヨーロッパに上陸したら、コカ・コーラも一緒に上陸した。アメリカ軍が日本を打ち破って日本に上陸したら、コカ・コーラもまた一緒に上陸した。
コカ・コーラはまさにアメリカの文化の象徴であり続け、それは今もまだ続いている。
アメリカ人にとって、コカ・コーラが買えない国は抑圧された国という定義なのだ。逆に言えば、コカ・コーラが買えるようになって、はじめて文明国になるという定義だろうか。
日本も戦後になってはじめて文明国になったとアメリカ人は認識している。なぜか。戦後からコカ・コーラが飲めるようになったからである。
コカ・コーラはイランでも飲まれている。エジプトでもヨルダンでも飲まれている。広大な大自然が広がるアフリカ大陸でも、各国でコカ・コーラのロゴが街に踊り、コカ・コーラのスタンドがあり、どこでもそれを飲むことができる。
「西洋文化は罪だ」と叫んで少女たち270名を誘拐したイスラム過激組織「ボコ・ハラム」が暗躍するナイジェリアでも、調べてみたら、ちゃんとコカ・コーラを売っている。ナイジェリア人もまたコカ・コーラを飲んでいるのだ。
まさか、ボコ・ハラムの連中はコカ・コーラを飲んでいないと思うが、もし飲んでいたら、それこそ「西洋かぶれ」として処刑が必要だろう。
しかし、コカ・コーラはアラビア語のロゴもあって、イスラム教徒もそれを飲み干している。子どもの頃からコカ・コーラが当たり前にあると、それを自国の飲み物だと勘違いするイスラム教徒もいるかもしれない。