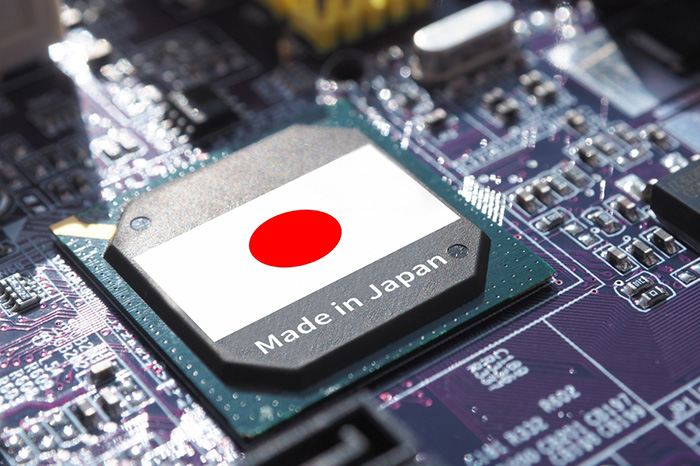ラピダスは復興シンボルへ
TSMC熊本工場の動きは、半導体国策企業のラピダス発展へと繋がる要素を持っている。それは、前記の日本が擁する半導体の発展3要素が生きるからだ。ラピダスは、北海道千歳市へ工場を建設中である。鹿島が建設を担う。TSMC熊本工場とまったく同じ構図である。
ラピダスは、日本の半導体技術が現在「40ナノ」レベルであるにもかかわらず、「2ナノ」を足がかりにして、さらに「1ナノ」へステップ・アップする大計画である。半導体事情に詳しくない者には、月へ石を投げるような無謀なことに映るようである。現に、日本の財務省はその立場だ。経済産業省が、自民党の支援でラピダスを発足させたことへ「無言」の批判の目を向けている。だが、これまでの日本半導体復興計画と異なるのは、過去の挫折を踏まえた慎重な計画に基づいている点にある。
日本半導体が、過去の復興計画で挫折したのは、かつての「栄光時代」を忘れられず「自前技術」へ固執しすぎた結果だ。ラピダスでは、こうした失敗に懲りて海外研究機関と技術提携する。また、ユーザーの需要を聞きながらも、単なる「御用聞き」で終わらず、それをラピダスも加わって半導体設計へ結びつける営業方針に立っていることだ。半導体企業としてみれば、構想の大転換と言える変革である。ラピダスの小池淳義社長は、次のように具体的な発言をしている。
半導体は、設計、ファウンドリー(前工程)、後工程の3つの部門間に厚い壁がある。これら部門間には意思疎通がない。中でも、一番大きな問題は設計部門である。半導体設計は、顧客企業に寄り添いながら半導体の最終製品をデザインする。同時に、ラピダスが必要な提案をして半導体を設計する、というものだ。つまり、ラピダスは単なる半導体受注企業ではなく、設計段階から参加してよりよい半導体づくりを支援する。これを、ラピダスの発展基盤にする、としている。
この実現には、ラピダス側にも相当高度の技術蓄積が必要になる。ここで生きてくるのが、内外の半導体研究機関との連携である。こういう非メモリー半導体受注企業は、世界にまだ存在しないという。ラピダスは、新しい半導体企業を目指しているのだ。
ラピダスが、「2ナノ」半導体製造で技術支援を受けるのはIBMだけでない。ベルギーの研究開発機関「imec(アイメック)」から技術指導を受ける。ラピダスは、量産に向けた技術検証の施設をまだ持っていないため、装置メーカーに加工を委託して半導体ウエハー(基板)を試作し、製造技術開発を急いでいる。
ラピダスは、「2ナノ」の次の段階で「1ナノ」へ進む。この技術では、東京大学やフランス半導体研究機関のLeti(レティ)と共同で次世代半導体設計の基礎技術を共同開発する。2024年にも人材交流や技術共有を本格化させるとしている。レティの半導体素子技術を生かし、自動運転や人工知能(AI)の性能向上に欠かせない1ナノ品の供給体制を構築する計画だ。
1ナノ品は、2030年代以降に普及が見込まれる半導体である。2ナノ品と比べ電力効率や演算性能が1~2割も高まるという。ラピダスは、将来の技術的発展を見据えているのだ。これを支援するのが、世界半導体研究のメッカとも呼べる超一流機関との提携である。繰返せば、米国IBM、ベルギーimec(アイメック)、フランスLeti(レティ)、そして東京大学である。