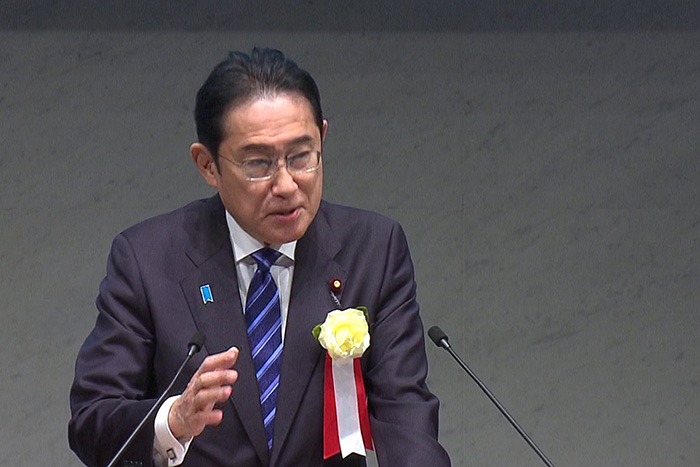黒田総裁を引き継いだ植田総裁もこの論理を継承しました。これは基本的に大規模緩和を続けるための「理屈」で、その点、国際金融圧力を真に受けた黒田総裁と、学者上がりの植田総裁とは受け止めが異なりました。
国際金融資本は中国への影響を考え、欧米の利上げの尻ぬぐいを日銀にやらせようとしました。これは植田総裁にもポルトガルでのECBコンファレンスの場で、欧州勢から「日銀は利上げするな」と言われました。しかし、植田総裁はもともとYCCによる長期金利のコントロールに疑問を持っており、インフレの実績に応じて市場が国債売りを仕掛ける中で、無理に国債を買い支えるのは無理だと考えました。
そこで実際、7月、10月の会合でYCCの弾力化を進め、YCCの実質形骸化を進めました。これは長期金利の実質利上げととられ、「利上げ」に反対する政府が出口策を検討していた日銀に圧力をかけました。
やむなく日銀は12月の会合で、賃上げの見込みが立たないとして出口策をあきらめ、緩和の継続を決めました。
賃金物価の好循環は絵に描いた餅
ここに日銀の物価安定目標は、事実上「賃上げ目標」の様相を強めることとなりました。
しかし世界に賃上げ目標を掲げる中銀がないように、金融政策で賃金を引き上げるルートはありません。せいぜい、金融緩和で経済成長を支援し、成長率の上昇が賃金増につながるルートに期待するしかありません。
ところが、多くの中銀が認めるように、金融緩和で成長率やインフレを押し上げることは困難と認識されています。
それだけでなく、政府日銀が期待する「賃金物価の好循環」は絵に描いた餅で、現実には「悪循環」がほとんどです。
つまり、企業が賃上げをし、人件費コストが高まるとその分価格転嫁してまたインフレが加速します。イタチごっこで、物価上昇に歯止めがかからず、実質賃金は物価高に負けて減少しやすくなります。