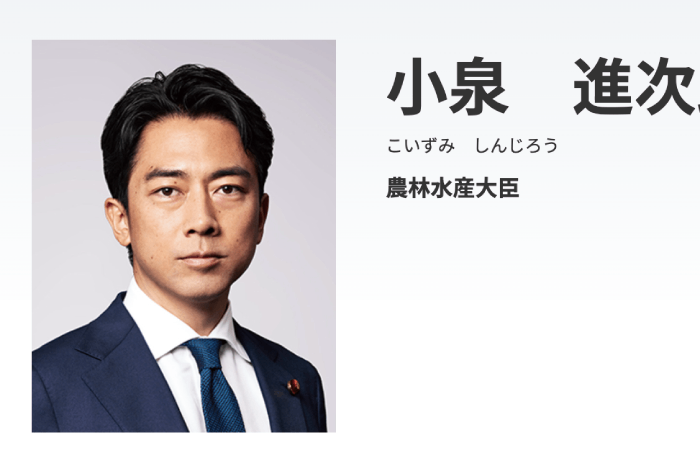「CFR」の排除と外交方針の変化
これらの新しい「ジャパン・ハンドラー」が推進する外交政策こそ、「アメリカ・ファースト」だ。前回にも書いたように、これはアメリカの国益の維持を最優先にして、同盟国も含め、すべての国々をアメリカの方針に従わせるという戦略だ。バイデン政権までのアメリカは、政権が民主党であれ共和党であれ、外交方針には継続性があった。それは、アメリカがその国益を短期的に妥協したとしても、アメリカ中心の安定した国際秩序を同盟国と協調して構築し、アメリカの覇権が結果的には維持できる長期的な利益を追求するというものだ。
ところが、トランプ政権の「アメリカ・ファースト」はそうではない。トランプ政権は安定した国際秩序の維持には関心がない。あらゆる国際関係でアメリカの利益を最優先で追求し、同盟国であろうがなかろうが、他の国々にはアメリカの国益の尊重を強く迫る。こうした方針だ。
一方、アメリカの覇権維持に向けた外交政策は、軍産複合体とウォールストリートを中心に結成されたシンクタンク、「外交問題評議会(CFR)」によって立案されてきた。
「CFR」が追求しているのは、グローバリストの世界戦略である。主権国家を乗り越えた世界政府統一中心の「ニューワールドオーダー(NWO)」を形成し、アメリカの超富裕層が世界中で規制なしに自由に投資できる、資本主義の世界的なシステムの構築を目指す。
「CFR」の政治的な影響力は絶大である。歴代政権の外交政策は国務省の部局、「政策企画本部」によって立案される。この部局の部長は「CFR」のメンバーであることが多い。「政策企画本部」は「CFR」からの指示と要望にしたがって、アメリカの外交政策を立案するという関係にある。
このような「CFR」は、バイデン政権までのの外交政策を全面的に担っていた。一方、前トランプ政権では「CFR」のメンバーは閣僚ポストからすべて排除されていた。「CFR」の影響下にある「政策企画本部」の部長さえも、トランプ政権下では「CFR」のメンバーではなかった。
一時は「CFR」がトランプ政権に擦り寄る態度も見せたものの、今回のトランプ政権でも「CFR」とは鋭い緊張関係にある。「CFR」はトランプ政権の外交政策の立案からは完全に排除されている。トランプ政権の閣僚には、「CFR」のメンバーはいない。
「政策企画本部」局長のマイケル・アントン
そして、これまで「CFR」の外交方針を具体的な外交政策に落とし込む役割であった国務省、「政策企画本部」を統括する局長も「CFR」に敵対的な人物に変わった。マイケル・アントンである。
マイケル・アントンは、米国の外交政策において「アメリカ・ファースト」の理念を中心に据え、国家安全保障と経済政策の統合、同盟国との関係再構築、そして専門的な交渉能力を活かした実務的なアプローチを展開している。彼の指導の下、政策立案局は米国の国益を最優先に考えた戦略的な外交政策を推進している人物だ。彼が出している方針こそ、現在のトランプ政権の外交政策を強く反映したものである。
それは、次のような政策だ。
<1. 「アメリカ・ファースト」戦略の推進>
マイケル・アントンは、ドナルド・トランプ前大統領の国家安全保障会議(NSC)でスポークスマンを務めた経験があり、トランプ政権の「アメリカ・ファースト」政策の主要な支持者として知られている。彼の外交政策の基本的な立場は、米国の主権と国益を最優先し、多国間主義よりも二国間交渉を重視することにある。このアプローチは、同盟国との関係においても、米国の利益を最前面に据える姿勢を示している。
<2. イラン核交渉における技術的リーダーシップ>
2025年4月、アントンはイランとの核問題に関する技術的交渉チームのリーダーに任命された。この交渉は、オマーンで行われる高官級協議と並行して進められ、ローマでの前回の協議では、両国が潜在的な核合意の枠組みを策定することで合意した。アントンの任命は、専門的な知識と経験を活かして、米国の立場を強化する意図があると考えられる。
<3. 国家安全保障と経済政策の融合>
アントンは、国家安全保障と経済政策の統合を重視している。彼の経歴には、「ブラックロック」のマネージングディレクターとしての経験があり、経済と安全保障の相互関係を深く理解している。この視点から、彼は経済的手段を活用して外交政策の目標を達成する戦略を支持している。