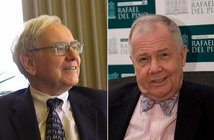ジョージ・ソロスは今年に入って、S&P500をショート(売る)するポジションを2倍に拡大しています。年始からトレーディングに復帰し、人民元を売る機会を伺ってもいます。この人民元ショートのポジションはソロスだけでなく、例えばカイル・バスやスタンレー・ドラッケンミラーも同じ立場です。
「あのソロスが」ということで、もしかすると今後、最悪は世界恐慌になるかもしれないと不安に感じている人もいるのではないでしょうか?そこで本稿では、「そもそも過去にソロスは、どれぐらいの精度で予想を的中させてきたのか?」を検証してみます。(『ウォーレン・バフェットに学ぶ!1分でわかる株式投資~雪ダルマ式に資産が増える52の教え~』東条雅彦)
世界が注目する「ソロスの予想」はどれほど当たるのか?徹底検証
市場崩壊に備える
2016年に入り、ジョージ・ソロスは世界経済の行く末をとても懸念しています。中国経済のハードランディングは「事実上不回避」だとしています。
今や世界第2位の経済大国である中国が落ち込むことで、世界的な不況と、市場の値下がりを予想しています。
今のところ、ソロスの読み通り、人民元(USD/CNY)はどんどん下落しています。また最近の報道で、S&P500の下落に倍賭けをしていることも明らかになっています。
ソロスによるS&P500連動ETFのプットオプション保有数は、2016年3月31日の210万口から、2016年6月30日の約400万口にまで倍増しました。プットオプションとは「売る権利」のことで、株価があらかじめ決められた価格をこえて大幅に下落すればするほど、莫大な利益になります。
また金の保有、金鉱株までも大幅にポジションを縮小しています。本来、金のポジションはリセッションがあっても安全だとされているにも関わらず手放したことから、相当な警戒感を持っていることは確かでしょう。
ソロスファンドの最新状況は、11月15日に米SECへの報告により明らかにされますが、その動向にも依然、注目が集まるところです。
そんなソロスは、前回のリセッションにあたるリーマン・ショック(2008年)を的中させ、その前後に2冊の本を上梓しています。この「予言書」とも呼ぶべき書籍を題材に、ソロスは金融危機の前後にどのような予想を行い、どのぐらいの精度で当たったのか?それとも外れたのか?を検証するのが本稿の趣旨です。
2冊の「予言書」
ソロスは、2008年9月15日に発生したリーマン・ショックを事前に予想していました。そして、リーマン・ショック前と後に、次の2冊を上梓しています。
1冊目(リーマン・ショック前)
(書籍名)
『ソロスは警告する 超バブル崩壊=悪夢のシナリオ』
(原著名)
The New Paradigm for Financial Markets Large Print Edition: The Credit Crash of 2008 and What it Means
(リリース日)
原著:2008年5月5日 邦訳:2008年9月2日
2冊目(リーマン・ショック後)
(書籍名)
『ソロスは警告する 2009─恐慌へのカウントダウン』
(原著名)
The Crash of 2008 and What it Means: The New Paradigm for Financial Markets
(リリース日)
原著:2009年3月30日 邦訳:2009年6月12日
1冊目の『ソロスは警告する』は、本がリリースされてから3カ月後(日本では2週間後)にリーマン・ショックが発生したことから、当時「予言書」として大いに売れて、世界的なベストセラーになりました。
ソロスは書籍の中で、「世界の現実的な姿」が、本当の世界との間で大きく乖離している点を指摘しました。
そして、サブプライム住宅ローンのバブル崩壊を見事に的中させた翌年、続編となる2冊目の『ソロスは警告する 2009』をリリースしました。この2冊目では、リーマン・ショックの振り返りと総括、自分の行った投資の状況報告、そして、今後の展開予想が述べられています。
2冊とも、ソロスの持論である「再帰性理論」について多くのページが割かれているのですが、本稿ではソロスの予想部分のみを取り上げて検証します(再帰性理論については次回メルマガで詳しく解説します)。
リーマン・ショック前の「ソロス予想」はどれくらい的中した?
1冊目『ソロスは警告する』は、リーマン・ショックの3カ月前にリリースされました。この時点ではソロスも、「リーマン・ブラザーズ」という投資銀行が倒産してしまうところまでは予想していません。
ただ、米国で盛り上がっていた住宅バブルの崩壊に伴って、世界的なリセッションが発生するところまでは予想していました。具体的には次の通りです。
予想1『サブプライム住宅ローンバブルの崩壊と金融危機』
やがて、アメリカ政府は税金を投入して住宅価格の下落を食い止めなくてはならなくなるだろう。その決断がくだされるまで、住宅価格の下落は加速度的に進行し、担保割れ住宅からは持ち主が逃げ去り、破綻する金融機関の数がどんどん増え、ドル離れの動きも不況も悪化するはずである。(P217より引用)
『ソロスは警告する』の中でも、まさに中核となっている警告内容です。この内容はスバリ的中します。
2008年9月15日にリーマン・ブラザーズが倒産して、高い信用力を持っていたAIG、ファニーメイやフレディマックが国有化される事態にまで発展しました。ベアー・スターンズはリーマン・ショック前の2008年5月30日に、JPモルガン・チェースに救済買収されました。
当時、米国の住宅価格が同時多発的に下落するのは、70年に1度と見積もられていました。破綻した金融機関はサブプライムローンの1年間の破綻確率を70分の1と計算して、1.4%(1÷70)に設定していました。この年間1.43%をベースにCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の価格を設定していました。大雑把に言えば、住宅ローン3000万円の保証を1年間43万円で引き受けていたのです。
しかし元々、破綻確率を時間で割る(タイムスライスする)のは間違っています。なぜならそれは、まるで70発の球数を持つピストルを手に持ち、「70発中、実弾は1発しか入っていないので大丈夫ですよ」と言って、1年に1回、自分に向けて発砲するかのような行為だからです。
3000万円の保証を年間43万円で引き受けられる状況は、ピストルのシリンダーを時計回りに1年に1つずつ回転させていき、70年後に実弾が発射されるという特殊な条件だった場合のみです。それだったら、3010万円(42万円×70年)を得ているので、70年後に生じる3000万円の損失をカバーできます。
しかし、現実にはそんな条件になっているはずもなく、毎年、ピストルのシリンダーをロシアンルーレットのように回転させて、引き金を引いて、1回カチッとやっています。
バフェットはCDSのような金融派生商品を「金融の大量破壊兵器」だとして、広く投資家に注意を呼び掛けています。
最もCDSを売りまくっていたAIGは、保険屋さんの確率理論で、より多くのCDSという保険を売れば売るほどリスクが分散されると勘違いしていました。サブプライムローン自体の損失よりも、このCDSにより、リーマン・ブラザーズ、ベアー・スターンズ、AIG等は破産に向かったのです。
そして、なぜかリーマン・ブラザーズだけが救済されずに倒産してしまいます。ソロスは次の2冊目の書籍で世界恐慌を危惧して、リーマン・ブラザーズも救済すべきだったとしています。