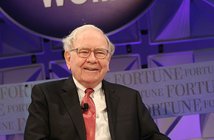日銀会合のたび、黒田総裁の発言に注目が集まりますが、金融政策とは改めてどういったものなのか。そこで今回は、その内容の解説と歴史を紐解いて解説する。(『牛さん熊さんの本日の債券』久保田博幸)
※『牛さん熊さんの本日の債券』は、毎営業日の朝と夕方に発行いたします。また、昼にコラムの配信も行ないます。興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
中央銀行が行う金融政策とは、いったい何なのか
金融政策とは、通貨を安定させることで経済発展に働きかけること
日銀のサイト内に「おしえて日銀」というコーナーがある。このなかで「金融政策とは何ですか?」という問いに対する答えが下記のようになっていた。
日本銀行は、わが国の中央銀行として、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資するため、通貨および金融の調節を行うこととされています(日本銀行法第1条、第2条)。
調節にあたっては、公開市場操作(オペレーション)などの手段を用いて、長短金利の誘導や、資産の買入れ等を行っています。こうした中央銀行が行う通貨および金融の調節を「金融政策」といいます。
物価の安定、それはつまり通貨価値を安定させることによって、経済発展に働きかけようとするものが金融政策といえる。政府がお金を使って公共投資などを行う財政政策とともに金融政策は経済政策の二本柱のひとつとなっている。
中央銀行は「銀行の銀行」という役割を担っていることから、中央銀行が民間銀行にお金を貸す際の金利が存在する。民間銀行が企業などにお金を貸す際の金利は、日銀の貸出金利が基準となっていた。この金利が「公定歩合」である。国内の基準金利である公定歩合を動かすことによって、物価や景気に影響を与えようとするのが金融政策となった。
この公定歩合を委員会制度として決定することにしたのがFRBであった。1913年に12の地区連邦準備銀行と、これを監督する連邦準備委員会がワシントンに設立された。中央銀行の設立には引き続き反対意見も多かったことから、全米の12地区に地区連邦準備銀行を設立し、それぞれの地区で銀行券である連邦準備券が発行され、各行ごとに公定歩合(民間銀行へ貸し付けを行うとき、適用される基準金利)が設定されることとなったのである。
恐慌による不況を回避すべく設立された米国の中央銀行であったが、設立直後に大恐慌を迎えてしまうことになる。これを受けて、地方分権型ではなく中央集権的な金融政策の運営が求められた。
1933年に連邦準備の機構が改革され、理事会の権限が強化された。金融政策を決定するための組織として連邦公開市場委員会(FOMC)が設けられたのである。
日本でこのような中央銀行の金融政策を決定するために、委員会制度が設けられたのは戦後となった。1949年に日銀法が一部改正され、日銀の最高意思決定機関として政策委員会が設置され、公定歩合の変更はこの政策委員会が決めることになった。しかし、この旧法による政策委員会は「スリーピングボード」などとも揶揄されていた。日銀の事実上の意思決定機関は総裁、副総裁、理事らで形成されている役員集会、通称、「円卓」であったとも言われた。このため、1998年4月1日に施行された日本銀行法(新日銀法)により、現在のかたちの委員会制度にあらためられた。
イングランド銀行では、1997年に財務省から中央銀行であるイングランド銀行に金融政策の決定権が移され、金融政策を決める金融政策委員会(MPC)が政策遂行のために新設された。
※『牛さん熊さんの本日の債券』は、毎営業日の朝と夕方に発行いたします。また、昼にコラムの配信も行ないます。興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
image by : slyellow / Shutterstock.com
『牛さん熊さんの本日の債券』2019年7月29日号より
※記事タイトル・リード文・本文見出しはMONEY VOICE編集部による
初月無料お試し購読OK!有料メルマガ好評配信中
牛さん熊さんの本日の債券
[月額1,100円(税込) 毎週月・火・水・木・金曜日(祝祭日・年末年始を除く)]
金融サイトの草分け的な存在となっている「債券ディーリングルーム」の人気コンテンツ、「牛さん熊さんの本日の債券」がメルマガとなりました。毎営業日の朝と引け後に、当日の債券市場を中心とした金融市場の動きを会話形式にてお伝えします。さらっと読めて、しっかりわかるとの評判をいただいている「牛さん熊さんの本日の債券」をこの機会にぜひ御購読いただければと思います。