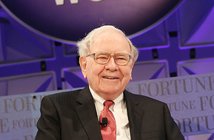日米首脳会談終了後、今国会中に安倍政権は退陣を決断するかもしれません。その後の政権混乱は、どんな形で市場や経済に影響を与えるのかを考えます。(『マンさんの経済あらかると』斎藤満)
※本記事は、『マンさんの経済あらかると』2018年4月18日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
プロフィール:斎藤満(さいとうみつる)
1951年、東京生まれ。グローバル・エコノミスト。一橋大学卒業後、三和銀行に入行。資金為替部時代にニューヨークへ赴任、シニアエコノミストとしてワシントンの動き、とくにFRBの金融政策を探る。その後、三和銀行資金為替部チーフエコノミスト、三和証券調査部長、UFJつばさ証券投資調査部長・チーフエコノミスト、東海東京証券チーフエコノミストを経て2014年6月より独立して現職。為替や金利が動く裏で何が起こっているかを分析している。
アベノミクス終焉でも影響は限定的。長い目でみれば経済は上向く
政治リスクを市場は無視できない
内外の政治リスクが高まっているとの認識は広まっている一方で、市場や経済への影響については「無視できる」あるいはあえて「無視すべき」とのコメントが有力投資家からも聞かれます。
しかし、米中貿易戦争こそ大騒ぎさせた一方で「やらせ」的な面が露呈しましたが、差し迫る内外の政治リスクには、無視できないものがあります。
確かに「米中貿易戦争」はプロレスショー的な面があり、トランプ大統領が秋の中間選挙を意識してあえて「危機感」を募らせている面はあります。最終的には中国の譲歩を引き出して「戦争」は回避される、と足元を見られ始めました。日本の鉄鋼、アルミ・メーカーへの関税増の影響も限定的とされます。
また、シリアへのミサイル攻撃も、中間選挙を狙った「やらせ」的な面が指摘され、一部には化学兵器の使用は、シリアではなく、イスラエルや米国の諜報機関が画策したもので、シリアが使用したと言うのは「濡れ衣」との見方さえあります。
それでもこの問題はこれで終わりでなく、次のイラン攻撃への伏線、という面があります。そのためにあえてロシアとの関係を悪く見せる「工作」もしたようで、その点でもプロレスショー的な側面は否めませんが、結果としてロシア・ルーブルやロシア株は急落し、新興国通貨も大きく下落しています。さらにブレントの先物が70ドルを超えるなど、原油価格も上がっています。
ワシントンの求心力回復、中間選挙へのキャンペーンでは済まされない影響が現実に市場に、そして海外経済に出始めています。
今後、米朝会談の結果いかんで、朝鮮半島情勢、北東アジアの地政学、核のリスク、日本の核戦略などに大きな影響が及ぶ可能性があります。そして日米関係も動いています。
そこで、以下では安倍政権混乱がこれからどんな形で市場や経済に影響するか、考えてみましょう。政権混乱には、安倍政権の弱体化による影響と、政権が交代した時の影響とがあります。
安倍政権の弱体化がもたらす悪影響
安倍政権の弱体化が、ここへきて急ピッチで進んでいます。森友学園問題では資料の書き換えが問題となりましたが、さらに不当な値引きに対して口裏合わせをしていたことが露呈し、政府の「うそ」が国民に広く疑われるようになり、加計学園問題では、総理秘書官が「首相案件」と言って圧力をかけていたことが暴露されました。
さらに自衛隊の「ない」はずの日報が出てきて、「戦闘」の文字が数多く見られ、非戦闘地域への派遣という政府の説明が覆されました。安保関連法案自体もうその説明の中で強行採決されたことになります。
そこへ財務省事務次官のセクハラ疑惑で、その問題自体はともかく、これへの財務省ならびに政府の対応が、非常識で、政府官僚への信頼を著しく傷つける結果となりました。
これら一連の事件発覚で、野党はもとより、与党内からも安倍退陣を求める声が出る始末。本人だけが今後の外交成果にかけて、また居座るつもりのようです。
NNNの世論調査では支持率が26.7%と、ついに30%を割り込みました。この安倍政権混乱は米国の耳にも入っているはずです。その米国とこの状況で日米首脳会談を持つことになりました。